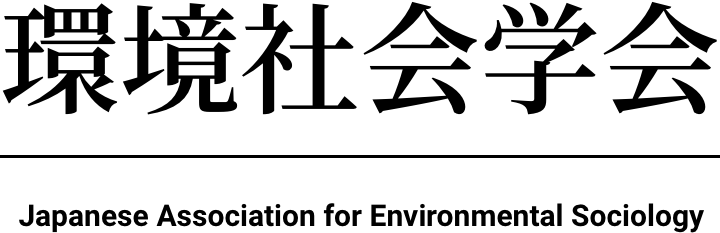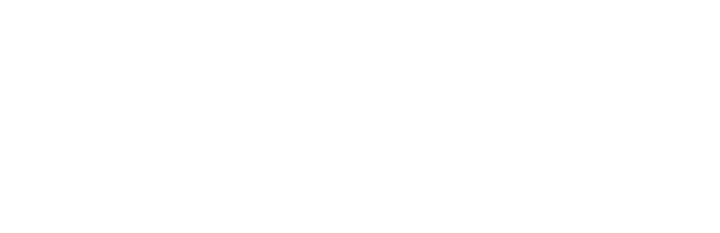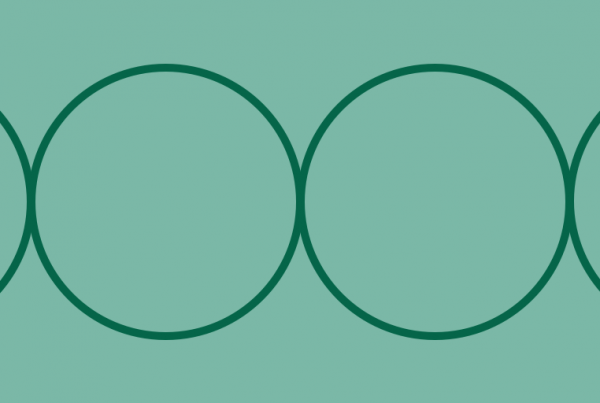第72回環境社会学会大会を12月6日(土)に奈良教育大学にて開催します。多数のご参加をお待ちしております。
※自由報告・実践報告募集のお知らせを掲載しました
※大会シンポジウムについて掲載しました
大会概要
- 日時 2025年12月6日(土)
- 会場 奈良教育大学
https://www.nara-edu.ac.jp/access/ - 対面、終日開催を予定
- 大会開催校:奈良教育大学(開催校事務局長・渡邉伸一)
自由報告・実践報告の募集
◇報告申込案内
- 報告時間:自由報告・実践報告ともに1報告あたり35分(報告20分+質疑15分)を基本とします(報告数により変更になる場合があります)。
- 申込期間:2025年10月15日(水)〜11月6日(木)
- 申込方法:下記の宛先へEメールにてご応募ください
※非会員の方は、申込時までに入会手続きおよび会費納入をお済ませください。
※会員の方は、申込時までに年会費の納入をお済ませください。
※年会費の未納期間がある場合は報告できないことがありますのでご注意ください。
※申込締切から1週間程度で担当より受理/不受理の通知をお送りします。
※申込が受理されましたら、必ず大会の参加申込みも行ってください。参加申込みがない場合は報告をお断りする場合があります。
◇申し込み時のメール記載事項
- 報告種別(自由報告/実践報告)
- 報告タイトル
- 報告者氏名・所属
- 連絡先(住所・電話・Email)
- 報告要旨
- 使用希望機器
※以上6点を記載ください。
※報告要旨は下記の形式を遵守のうえ、WordファイルおよびPDFファイルの双方を提出ください。
※使用希望機器は会場の都合で希望に添えない場合もあります。
◇報告要旨の形式
- 要旨集は各報告2頁(A4)で組みます。1頁あたり40字×40行で、冒頭1行目を空けてください。
- 報告タイトルと報告者氏名・所属、参考文献等を含め、2頁以内に収まるように字数を調整してください。報告タイトル、報告者氏名・所属、本文は文字の大きさを10.5ポイントとしてください。
- 誤字脱字、内容に関する引用トラブル、形式からの逸脱等により、要旨集の作成に支障をきたす事例が相次いでおります。ご自身によるチェックの徹底をお願い致します。
- 要旨集に掲載されたタイトルを報告時に変更することはできませんのでご留意ください。
◇実践報告について
- 実践家・NGO・NPOとの連携を推し進めるため、第62回大会より「実践報告」の枠を設けています。
- 環境社会学会の特徴として、現場・現実社会との緊張関係の中での学問的模索から、多様な展開が生まれてきたことがあります。学会大会においても、実践活動をされている方々の報告機会を増やすことで、会員同士の学的交流・実践的交流をさらに活性化させたいと考えています。従来の自由報告の枠に収まりきらない、実践家、NGO・NPO、行政職員等の立場でご活躍されている学会員の実践的な取り組みをご報告いただく機会として、ご活用ください。
- なお、エビデンスに基づかない報告や、政治的主張のみを目的とした報告については、発表をご遠慮いただく場合があります。
◇申込み・問い合わせ先(自由報告・実践報告担当)
野田岳仁(法政大学) noda[at]hosei.ac.jp
船木大資(金沢星稜大学) dfunaki[at]seiryo-u.ac.jp
紀平真理子(名古屋大学) kihira.mariko.k3[at]f.mail.nagoya-u.ac.jp
※[at]を@に変換して送信してください。
参加費・参加申込
<準備中>
宿泊について(重要)
今大会では宿泊施設の斡旋は行いません。奈良市および周辺地域は宿泊施設が限られており、大阪など近隣都市にご宿泊の場合も、時期が近づくと手頃な宿泊先の確保が難しくなります。お早めのご予約をお勧めします。
託児サービス利用補助制度のご案内
<準備中>
大会シンポジウム「人と自然のインタラクションⅡ:関係性価値と環境社会学」
【登壇者】
報告者:石原広恵(東京大学)、篭橋一輝(南山大学)、大門信也(関西大学)、谷川彩月(人間環境大学)
司会・解題:福永真弓(東京大学)
【趣旨】
今日、「自然」は保全や保護の対象として囲い込まれる一方で、気候危機の時代のレジリエンスおよびリスク管理の基盤として、また都市や地域のウェルビーイングやコミュニティ形成を支えるインフラとして制度的に再編されつつある。さらに、サステナブル・ファイナンスに象徴される環境の金融化や商品化が加速し、政策設計と科学技術の結びつきもかつてなく緊密になっている。里山保全、市民参加型モニタリング、ブルーカーボン、グリーンインフラといった実践に見られるように、生活世界に根ざしていた「自然」もまた、グローバルなサステナビリティ・レジームのもとで再編・制度化され、政策や経済活動の対象として積極的に管理されるようになっ ている。
これまで環境社会学は、身近な自然や生活世界における人と自然の関係性に関する研究を積み重ね、近代社会の基盤となってきた自然の外部化や人間と自然の二元論的思考を批判的に問い直してきた。しかしながら、気候危機が大きく世界の政治的状況と絡み合いながら私たちの生活を根本的に変えようとしている現在、環境社会学もまた、変容する人と自然の関係性に応答した学問的展開を試みる必要があろう。
商品化や金融化とともに急速に進展している、市場経済による自然の内部化について、環境社会学はどのような立場から議論しうるのか。サステナビリティ・レジームのもと社会変革が求められるなか、公正さと正義はいかに実現しうるのか。そして、自然をつくり管理する時代において、ガバナンスを導くのはどのような価値であり、規範なのか。
これらの問いは、気候危機と生物多様性のネクサスをいかに構築するかが学問的にも社会的・経済的にも喫緊の課題となるなか、ますます重要さを増している。とりわけ、人と自然の関係を実践的に把握し、理解すると同時に、これからの人と自然の関係性を思考するための柱となる価値と規範に関する研究は、広く分野をまたぐ喫緊の課題となっている。
本シンポジウムでは、IPBES(生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)が提唱する「関係性価値(relational values)」の概念と、これまで環境社会学が蓄積してきた議論を交差させ、その相互展開の可能性を探る。関係性価値は、生態系や自然との関わりにおける人々の感情的・倫理的・文化的価値を重視する枠組みであり、従来の交換可能な経済的価値や内在的価値では捉えきれない関係性の層を明らかにしようとする試みである。日本の環境社会学は、コモンズ論、生活環境主義、生身・切り身論、人とモノの関係誌、レジティマシー論などを通じて、日常生活における自然の意味づけとそのガバ ナンスを丹念に記述し、科学や政策の言語だけでは捉えきれない自然との関係性の厚みを明らかにしてきた。いまやIPBESが関係性価値を世界的に位置づけようとするなかで、環境社会学が学問的・実践的にいかなる貢献をなしうるのかをあらためて検討したい。
(研究活動委員会)