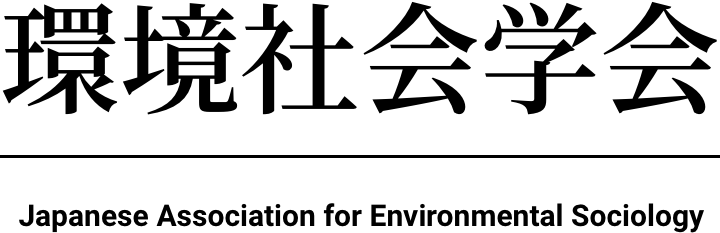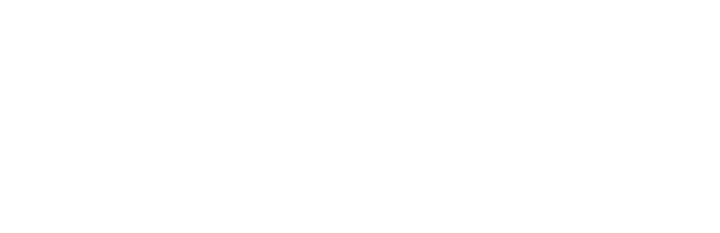第8回環境社会学会奨励賞が以下の通り論文1点、図書2点に授与されました。第9回環境社会学会奨励賞にも積極的なご推薦をお願い申し上げます。以下は受賞理由と受賞者の言葉です。
論文の部:船木大資,2023,「自然保護地域におけるローカルな歴史の遺産化―斜里町・しれとこ100平方メートル運動の事例から」『環境社会学研究』29:138-152.
受賞理由
本論文は、斜里町のしれとこ100平方メートル運動を事例として、当初「原生自然保護」のフレームワークで行われていた運動が、ある写真家の活動をきっかけに開拓民の歴史を肯定的なものとして資源化、遺産化するようになった経緯を描き、その意義を探った論文である。社会的リンク論、生活環境主義、半栽培の社会学等、自然と人との関係をその歴史性から読み解いてきた環境社会学の議論をふまえつつも、さらに近年研究蓄積がなされてきた文化遺産の社会学を導入し、「単線的に進むのではなく複雑な関係のもとで絶えず更新・再構成される」という再帰的な遺産化のプロセスに迫ろうとした点に特徴がある。著者は事例分析をつうじて、「『原生自然保護』フレームが人びとの生活の履歴を不可視化する装置となる」という学問的指摘それ自体が、むしろ今日においては再帰的に人びとの実践のなかで語られ再文脈化されていることを説得的に示している。とりわけ「遺産化のプロセスは一方向的に「手つかずの自然」へと収斂していくわけでなく、そのときどきのアクターの関心を反映しながら更新されていく」という指摘は重要であり、今後環境社会学としてさらに検討されるべき論点だといえよう。今後ここで描かれた事例について、ナショナルトラストをはじめとする自然保護領域の議論、また歴史的環境の社会学における議論などと切り結びながら、より展開力のある論考へ深めていくことが期待される。
受賞のことば
この度は環境社会学会の奨励賞をいただくことができ、大変光栄に感じております。
本論文執筆にあたり、快く調査に応じてくださった皆様、ご指導いただきました先生・先輩方、論文を査読し、また評価してくださった環境社会学会の皆様に深く感謝申し上げます。
私が研究しております北海道の知床は、戦後豊かな自然が残っている地域として再発見され、以後国立公園や世界自然遺産などの自然保護地域制度によって守られてきた地域です。その一方で、古くは縄文時代から、アイヌ民族・和人にいたるまで、さまざまな人々が暮らしてきた場所でもありました。普段は「手つかずの自然」と認識されることの多い知床ですが、近年では、これらの人々の営みを内外に伝えていくような動きが現れています。本論文は、こうした動向のひとつである、農業開拓の歴史が自然保護運動において「遺産化」されていく過程を論じたものになります。
もちろん、これらの取り組みのすべてがうまくいっているわけではなく、また課題がないわけでもありません。遺産という現象が、ときには対立や軋轢をともないながら進行していくことは、すでに多くの研究によって明らかにされています。今後もこのような自然保護地域・自然遺産地域の動態について、環境社会学会員の皆様をはじめ、多くの方々と議論しながら探究していきたいと考えております。皆様には引き続きご指導いただけますと幸いです。
船木大資(金沢星稜大学)
著書の部:廣本由香, 2024, 『パインと移民―沖縄・石垣島のパイナップルをめぐる「植民地化」と「土着化」のモノグラフ』新泉社.
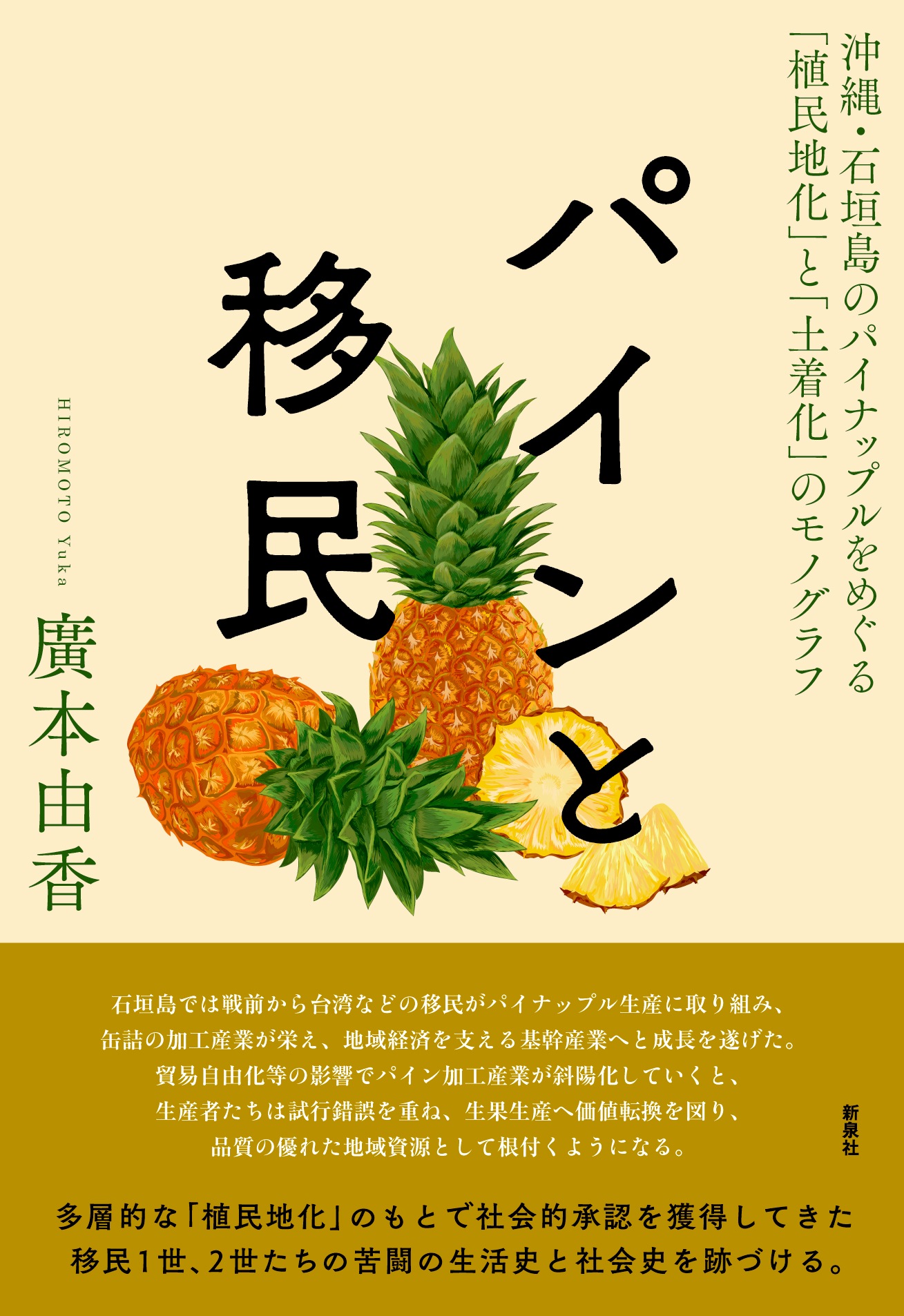
受賞理由
本書は沖縄の石垣島におけるパイナップル(パイン)生産をめぐって、戦前からその栽培を担ってきた台湾などの移民の生活環境史を多数の資料やインタビューを緻密に重ね合わせながら跡づけたモノグラフである。著者は実際にパインの出荷や事務の手伝いをしながら、10年間に及ぶフィールド調査を行った。パインは台風や干ばつに比較的強く、水はけが悪く痩せた土地でも栽培可能な農作物である。戦後復興期のパインブームが過ぎ去った後、改めてほかの作物には向かないという風土の弱みを、「この土壌が十分に活かせるのが何よりもパイン」だと品質を追求するモチベーションに転換し、缶詰の加工用原料から消費者に評価される生果の生産へと移行する。ここに、匿名の存在だった移民農家が生産者としての自律を目指す「土着化」の動きの契機が見出される。
本書はパイン生産や労働の意味を考える補助線として、ドイツの社会哲学者、A・ホネットの3段階の承認論を参照している。「パインと社会的承認」と題された終章では、多層的な「植民地化」のもとで、「よそ者」の移民はパイン生産を通じて地域における社会的存在意義をより確実なものにすべく「承認をめぐる闘争」を行ってきたと著者は結んでいる。ただし、ホネットを超えて「新たな視点としての社会的承認」論が発展的に論じられているかといえば、やや物足りない。とはいえ、本書は、「植民地」と「土着化」という、きわめて普遍的で重要な問題系をパインという農産物から解きほぐして描写した、オリジナリティに富んだすぐれた著作であることは間違いなく、環境社会学会奨励賞にふさわしい作品であることが認められる。
受賞のことば
このたびは学会奨励賞をいただき、ありがとうございます。たいへん嬉しく思いますし、今後の研究の励みにもなります。
本書は博士論文をもとに、その後も調査や研究を続けて書き上げたものです。私は博士課程中にパイン生産者のもとでアルバイトとして働きながらフィールド調査を続けました。手探り状態のままフィールドに飛び込んだ私が、最終的にこのような本を出版できるまでになったのも、ひとえにパイン生産者の方々や島の人びとのおかげです。
この本は、パイン生産に励んだ移民一世(台湾移民、県内移民)の歴史、生産地域の環境、そしてパイン生産を継いだ移民二世の実践的な取り組みに着目し、島嶼の地域経済を支えたパイン産業史や生活史を発達させてきたプロセスに迫っています。それは社会の中で「周辺化」「他者化」されてきた移民一世と二世の生産者が、厳しい環境と差別と闘いながらパイン生産を通して地域社会の中で居場所を築き、社会的承認を得てきた「土着化」の歩みでもありました。
私自身、地域社会の中で「周辺化」「他者化」された人びとの経験や実践に光を当てた生活史を記述する必要性や、その記録自体が社会的承認を広げる手助けとなり、地域文化の確立につながると考えてきたからです。今回の受賞も、そうした移民一世と二世のパイン生産者が歩んできたこれまでの軌跡が認められ、社会的承認が得られたという一つの証だと思い、たいへん嬉しく思います。
最後に、博士課程から現在に至るまで、自由気ままに調査・研究ができるような環境をつくってくださった先生方や現場の方々に、この場をお借りして感謝を申し上げます。ありがとうございました。
廣本由香(福島大学)
著書の部:松井理恵,2024,『大邱の敵産家屋―地域コミュニティと市民運動』共和国.
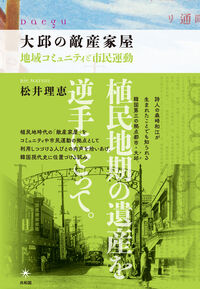
受賞理由
本書は、韓国大邱市にある植民地時代の日本式家屋群が、解放後、町工場の集積地として利用されてきたこと、さらに現在それを保存・活用しようという市民の運動があることに注目し、その意味について多角的に考察した本である。著者はこの本で、まず、大邱市の空間的な配置の変遷、当該家屋群を利用してきた人びとのかかわり、その人びとの間の関係を、地域の履歴として明らかにする。そして、再開発の中で工具商人や技術者たちがこの町に残ろうとしたことに注目し、その理由を、この町が蓄積した、資材や工具などをめぐる地域内流通や助け合い、さらにはそこから生まれた人びとの紐帯、といった「コモンズ」的なものに見いだした。そしてこの家屋群を保全・活用しようとする市民の運動が、なぜ植民地時代の建造物を歴史的環境として保全しようとするのかを徹底的に考えた。そうした、本書で引用されている言葉をそのまま使えば「抵抗と適応の総体的なプロセス」を、詳細なモノグラフとして描いた著作でもある。環境社会学がメインテーマの一つとして扱ってきた歴史的建造物やまちづくりについて、その議論をポスト・コロニアルの視点にまで広げ、深めた著作だとも言える。二次資料中心の記述になっていること、論証構成に粗さが残っていることなどが惜しい点としてあるが、それでも、「敵産家屋」という、「日本人」として語ることが困難な事例に挑み、また、植民地の記憶・経験を語ることの困難にも挑んだ点は高く評価できる。前にも後にも類書は出ないのではないかとも思わせる著作だった。
受賞のことば
拙著『大邱の敵産家屋』が環境社会学会奨励賞(著書の部)を受賞した、という思いがけない知らせに驚くとともに、大変光栄に存じます。研究歴に産休・育休の期間を含まないということで、拙著を選考の対象としてくださった奨励賞選考委員会の皆様に御礼申し上げます。
ちょうど20年前、初めて書いた論文が『環境社会学研究』に掲載されました。しかし、その直後、「私はなぜ韓国をフィールドとして研究するのか」という、大きな問いに直面して身動きが取れなくなってしまいました。拙著は、この問いに対して私自身が出した答えです。それだけに、他でもない環境社会学会で評価していただけたことを、何よりもうれしく思います。
この20年間、家族や友人たちからサポートを受け、子どもを育てながら研究を継続してきました。長期にわたってフィールドに入り、じっくり話を聞く、というスタイルの調査は、研究者人生のかなり初期の段階でできなくなりました。このような事情もあり、拙著は大邱で地道に調査を続けてきた市民運動家や研究者の成果をお借りして書き上げることになりました。今回の受賞を大邱にいる仲間たちと分かち合いたいです。
この原稿を執筆している最中に「この本を一般の読者に届けるのか、それとも研究書として世に出すのか」という岐路に立ちました。私は一般の読者に届ける、という選択をし、結果的に環境社会学に関する議論は大幅に削ることになりました。しかし、拙著のベースに環境社会学があるのは明らかです。拙著を手に取ってくださる方の多くが韓国や朝鮮半島に関心のある方のようですが、こういった環境社会学とはあまり縁のない読者に、拙著を届けることができたことは、環境社会学を学ぶ者としてうれしく思います。
一方、拙著を環境社会学にいかに位置づけるのか、という非常に重要な点が、積み残しとなっている状況です。この研究がなぜ環境社会学の成果なのか。日本だけでなく、韓国や東アジアの環境社会学者に説得力をもって伝えられるように、これからも研究に励む所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
松井理恵(跡見学園女子大学)