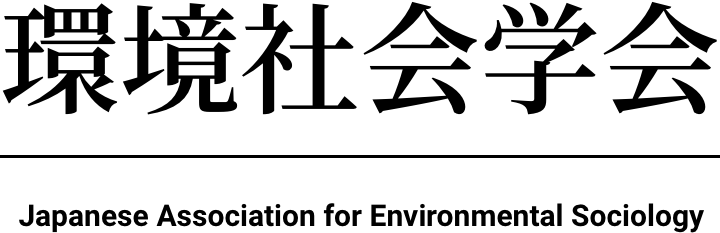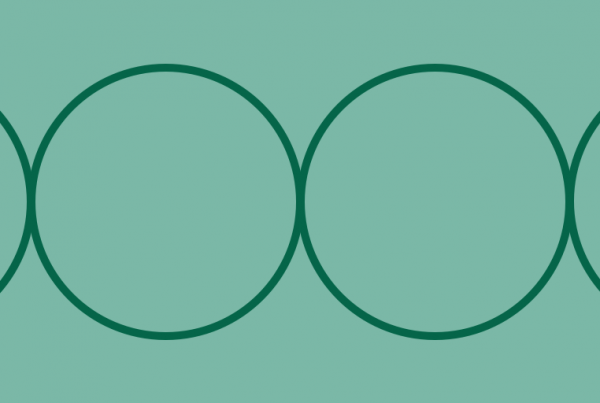環境社会学会は、2024年6月22日~23日に第69回大会をに京都教育大学藤森学舎にて開催しました。企画セッションと自由報告部会の報告を掲載します。
企画セッション1(研究活動委員会企画)「地域社会における軍事化の浸透と抗いの可能性」報告
熊本博之(明星大学)
「日本を取り巻く安全保障環境の悪化」というフレーズのもと、軍事施設の建設や拡張、他国軍との合同演習も含む軍事訓練などが、国内の様々な地域で進められている。その多くは周辺に位置する地域であり、それらの地域では「何かが徐々に、制度としての軍隊や軍事主義的基準に統制されたり、依拠したり、そこからその価値をひきだしたりするようになっていくプロセス」(シンシア・エンロー)である軍事化が浸透しつつある。そして防衛力の強化を好感する世論が軍事化を正当化するなか、問題は周辺へと押し付けられ、不可視化されている。
このような認識のもと、企画セッション1は、軍事化の浸透が進む地域で起きている問題の現状と、その現状への抵抗について、3つの報告をもとに検討し、この軍事化の進む社会における環境社会学の果たしうる役割について考える場となった。当日のプログラムは以下の通りである。
○ 趣旨説明 熊本博之
○ 第1報告 朝井志步(愛媛大学)「環境社会学の観点から軍事化が及ぼす影響について研究する意義」
○ 第2報告 熊本博之「沖縄社会における軍事化の浸透―2022県民意識調査より」
○ 第3報告 大野光明(滋賀県立大学)「織りなされる脱軍事化の営み―京都府京丹後市宇川における軍事化に抗する運動」
○ コメント 池尾靖志(立命館大学)
○ 全体のディスカッション
第1報告で朝井は、当事者の生活全般に及ぶ社会的側面から被害を捉え、意思決定における非対称性にも注目する環境社会学の視点が、地域社会における軍事化の浸透を解明する上で有効であることを示した。そして、「公が私に優先するという考え方の中に、公害の根源があった」という宇井純の言葉を引きながら、同様の傾向をもつ軍事問題に対しても、公に対して私の立場を徹底して拡張することで、国家の介入を押しとどめる抑止力になると主張した。
第2報告で熊本は、「中国の脅威」をはじめとする周辺環境の悪化の実感と、「国防は国家の専管事項」という論理で沖縄の自治を無化しながら辺野古での基地建設を進める政府の姿勢とが、特に若い世代における米軍基地の消極的受容傾向につながっていることを、2022年に実施した県民意識調査をもとに示した。このように軍事化は意図的に進められており、だからこそ必要なのは、軍事化を進める人たち、黙認する人たちの脱軍事化であることを指摘した。
第3報告の大野は、「日常は軍事化と脱軍事化のせめぎあいの現場」であるという認識のもと、米陸軍経ヶ岬通信所が建設された京丹後市宇川地区の人たちの「日常」に着目する。住民による運動/運動未満の活動の結節点としての「憂う会」と、住民にはできないことを担う外部の運動団体とが、お互いに補いあいながらネットワークを形成し、軍事化の及ぶ領域をひとつひとつ反転させていく営みに、脱軍事化の可能性を示した。
3つの報告に対して討論者の池尾から質問がなされた。やや強引にまとめれば、池尾からの質問に通底していたのは、米軍や自衛隊の基地が、地域に被害をもたらすと同時に、安全保障面における安心をももたらす存在であると住民に認識されていることに、どう向き合うのかというものだった。実際、熊本の報告でも、「日米安保体制は現在よりももっと強化するべきだ」という意見に対して、賛同38%、不賛同24%と割れるなか、「どちらともいえない」と答えた人も38%おり、判断に迷う沖縄の姿が浮かび上がる。
この池尾の問いに、当日は十分に答えることはできなかったが、このような認識が住民に生じている状況こそ、軍事化の浸透の表れである。今後のさらなる検討が求められる課題だといえよう。
続いてフロアからも、様々な質問がなされた。なかでも茅野会員からの、六ヶ所村での長期にわたる調査経験に基づいた質問が示唆に富んでいた。質問の1つは、時間の効果に関するもので、沖縄の基地問題も六ヶ所村の核燃施設に関する問題もあまりに時間が経過しており、若い世代にとってはもはや、変わり得ない構造であるかのように捉えられているのではという指摘である。この指摘には首肯するところが大きいが、茅野も触れていたように、だからこそ若い世代からは、基地や核燃施設とは違う観点から地域の未来を考えるような動きも見え始めている。そうした動きも、脱軍事化への営みとして丁寧に捉えていく必要があるといえよう。
また茅野からは、軍事政策が国家の論理で進められている以上、ナショナリズムへの言及も必要だろうという指摘もなされている。これについては、熊本の2022年調査でも主要な変数となっており、より重点的に分析を進めていく必要があると再認識させられた。
企画者たちはこれまで、環境社会学会の場において、軍事-環境-被害の関係性を問う報告を続けてきた。今回の企画セッションが、様々な意見が飛び交う、活気のあるセッションになったことは、これまでの私たちの研究活動が学会に根付いてきたことを感じさせてくれるものであった。今後も各々が研究を深めつつ、学会で報告していくことで、軍事化が進む社会において環境社会学がなし得ることは何か提起し続け、社会の脱軍事化に資するような成果を、会員の皆さまと共に考えていきたい。
企画セッション2(震災・原発事故特別委員会企画)「 『住む』ことへの介入に抗う/向き合うために――福島第一原発事故被害地域の現場から」報告
青木聡子(東北大学)
企画セッション「『住む』ことへの介入に抗う/向き合うために――福島第一原発事故被害地域の現場から」は、東日本大震災被災地のなかでも福島第一原発事故被害地域に特に焦点を定め、作為・不作為の双方によって被災者の生活再建を阻む力、なかでも「住む」ことへの介入について考えることを目的に、震災・原発事故特別委員会企画として開催した。
災害は人びとの生活に大きな被害をもたらすが、そのなかでも生活の基盤である「住む」ことは、災害そのものにより危機にさらされるだけでなく、その前後の人為的な施策や対応によってもさまざまな影響を受け、左右される。本セッションでは、震災前後の中長期的な施策や対応も含めて、被災者におよぶさまざまな外力を、「住む」ことへの介入と位置づけた。介入の影響としては、もともとの居住地に住み続けることを諦めさせるような形もあれば、避難先の新しい土地に住み直すことを阻害する形もある。本セッションでは三つの報告をもとに、「住む」ことへの介入の実態や、それによって生じる事態を明らかにし、それらへの向き合い方や抗い方について検討した。
第一報告「土地に根差すことへの介入――浪江町津島のディアスポラ」(関礼子・立教大学)では、計画避難区域への指定と帰還困難区域への区域再編により住民が「ふるさと」を追われることとなった福島県浪江町津島地区の事例から、事故後の作為・不作為だけでなく福島第一原発事故そのものが「住む」ことへの介入であったと指摘された。先祖や家族・親族とともに生活圏・津島(=「ふるさと」)のなかに根を下ろし住まうことを原発事故によって奪われた(=介入された)人びとは、それへの抗いとして、「ふるさとを返せ」訴訟を展開し生活圏の原状回復を求めてきた。さらに、屋敷の維持管理、津島の記録集や記録映像の作成、伝統芸能の継承、「家の葬式」、「家の遺影」などの個々の取り組みは、地域の記憶や記録を遺すという、ひいては≪ふるさと喪失≫を遺すという抗いでもあることが指摘された。
第二報告「原発事故被災者の避難先での生活再建とその困難――避難先に新たに住み直すことへの介入」(高木竜輔・尚絅学院大学)では、福島県富岡町からの避難者を事例に、人びとが避難先に住み直す際に、①市民権をめぐる困難、②政府の支援をめぐる困難、③コミュニティ形成の困難という三つの困難に直面すること、そしてそれらが事故被害の矮小化に基づく政府の作為(避難指示区域の線引きとそれによる各種分断の生成)と不作為(帰還を前提とした、避難先での支援の欠如)に起因していることが指摘された。こうした介入に対する抗いとしては、避難元の住民票を持ち続けることや、避難元と避難先とを行き来する「通い」という模索があることも示されたが、こうした「どっちつかず」を良しとせず帰還または住み直しのいずれかを迫る、制度的、社会的圧力の存在も指摘された。
第三報告「都市計画技術批判――原発事故『後』にするために」(窪田亜矢、東北大学)では、都市計画の名のもとに震災・原発事故以前からなされてきた「住む」ことへの介入が批判的に検討された。窪田氏によれば、そもそも住むという行為には何らかの介入をともなう。人びとは望ましい介入を積極的に受容し、望ましくない介入には抗い、介入を柔軟に取捨選択してきた。だが、原発誘致や復興計画・事業は、人びとに過重で連続的な抗いを強いることとなった。特に原発事故後においては、住民一人一人の要望よりも集合体としての都市のありかたを重視する都市計画の合理的思考が、地域社会の実態から乖離した復興を提示することになった。具体的には、町を更新するかたちでの復興(build back better)である。このような都市計画による介入に対しては、町を残すという抵抗が模索されてきたが、それらを無力化する制度的、社会的な力が働いていることも指摘された。
これらの報告を受けたディスカッションでは、まず報告者間で、環境的不正義の抑制はいかにして可能かや、適度な作為・不作為とはいかなるものかをめぐってやり取りがなされた。詳細は割愛するが、やや乱暴なまとめ方をすれば、焦点となっていたのはケイパビリティであったように思う。例えば、第二報告で紹介されたような、どっちつかずで一見すると「宙ぶらりん」な身の置き方も、住まい方の一つとして政策的に支援することや、第三報告で紹介されたような町外コミュニティの試みを制度的に可能にし政策的に支援することが求められよう。そのための都市計画の在り方としては、未来に選択の余地を残した「空地の思想」、環境社会学的に言えば順応的ガバナンスの考え方を取り入れることが有効と思われるが、インフラ整備など本来的に「堅い管理」を求められがちな都市計画にどこまで「柔らかさ」や余白を組み込めるのかが課題であろう。フロアからは、除染事業の有する両義性についてや、地域デザインを専門とする窪田氏からの問いかけに環境社会学はいかに答えるべきかをめぐって、熱いコメントが寄せられた。
本セッションは、直接的には東日本大震災の被災地域を対象としたが、企画にあたって念頭に置いていたのは、本年1月に発生した能登半島地震をめぐる「能登半島地震の被災地の復旧・復興は「将来の需要減少や維持管理コストも念頭に置き、住民の意向を踏まえ、十分な検討が必要だ」との発言(於:財務省税制制度等審議会、2024年4月9日)や、SNS上でも飛び交った、「条件不利地域」に住み続けることを非効率と切り捨てる声への危機感であった。そもそもこうした「効率よい住み方」を促す圧力は、震災をきっかけに登場したわけではなく、2000年代半ばごろから都市計画分野で「スマートな縮退(smart shrinking)」として肯定的に議論されてきた。このため今回のセッションでは、工学研究の立場から従来の都市計画を批判的に議論しておられる窪田氏に登壇していただいた。その窪田氏から発せられた「コミュニティを意識的に継承していこうとする試みを後押しする都市計画の在り方とはいかなるものか」という問いに、環境社会学がどのように応えうるのかは、今後も継続的に検討されるべき課題である。3名の報告者の方々、ならびに50名あまりのフロア参加者の方々、本セッションを一緒に企画・運営していただいた高﨑優子氏と廣本由香氏に心から感謝を申し上げたい。
企画セッション3「脱炭素に関わるドミナントストーリーと環境社会学―洋上風力発電を事例に」報告
西城戸誠(早稲田大学)
企画セッション「脱炭素に関わるドミナントストーリーと環境社会学―洋上風力発電を事例に」は、約40名の参加者がありました。同時間帯の自由報告セッションにおいて、再生可能エネルギーや気候変動に関する報告があり、これらの報告者とのディスカッションができなかったためプログラム編成に対して残念な思いをしましたが、2日目の午後という時間帯にもかかわらず多くの方に参加していただきました。改めて感謝申し上げます。
本セッションでは、地球環境主義的な観点から気候変動問題への対応として、自然環境と生活環境に配慮しながら洋上風力発電という近代技術を用いた事業に対して、環境社会学的な研究にどのような可能性があるのか、また気候変動の問題への応答、持続可能な社会やSDGsの希求といった、脱炭素(カーボンニュートラル)に関わるドミナントストーリー(支配的言説)が主流となる中で、環境社会学は何ができるのかという点を考えていくことを目的としていました。
第1報告「洋上風力発電事業の地域貢献策が果たす役割」(本巣芽美・名古屋大学)では、2つの洋上風力発電事業(港湾風車)における地域貢献策が住民からどのように受け入れられているのかをサーベイし、地域貢献策がほとんど認識されていないという点が示されました。地域の受容性を上げるという観点からは、具体的に地域貢献策の認知度の向上やニーズとのマッチングが問われつつも、洋上風力発電によるメリットやリスクを引き受ける「地域」はどこか(特に排他的経済水域における洋上風力発電)という問いや、地域の内発性の重視を相対化した上で、補償的受益ではない受益をどのように考えるかが環境社会学の課題であるという指摘をされました。
第2報告「洋上風力発電事業の案件形成過程における支配的フレームの変遷―山形県遊佐町沖を対象として」(平春来里・名古屋大学環境学研究科)では、遊佐沖の洋上風力発電を巡った案件形成過程に関する詳細な分析がなされ、一般海域の洋上風力発電に対する法律(再エネ海域利用法)に基づく法定協議会だけではない、都道府県や自治体独自に関係者の調整を図る仕組みが、地域の多様な声を事業者にとどけることに効果的であることが示されました。環境社会学では合意形成の場や合意形成のプロセスに関する研究蓄積はありますが、制度外に設置された合意形成、調整の仕組みが重要であることが再確認されたと思います。
第3報告「洋上風力発電の「開発フレーム」と地域社会の応答」(西城戸誠)は、漁業共生と地域共生のモデルとなった事例(長崎県五島市)と、そのフレームを受容した地域、漁協の応答に関する事例報告でした。開発フレームの受容を巡って地元住民や自治体も含めた「まちづくり」の観点から考える必要があり(制度転用の事例も含めて)、地域で「公論」を作るモデルの重要性や環境社会学の課題として、Good Practiceの発掘と「失敗例」との比較や、新しい価値をつくる、実践をした上での事後検証の可能性について指摘がありました。
これらの報告に対してコメンテーターの丸山康司さん(名古屋大学)からは、気候変動問題という抗いがたい前提がある中で、洋上風力発電が問題解決の「切り札」とされつつも、社会的課題が数多くあるという話がありました。また、環境社会学の役割の難しさと可能性についての指摘、3つの報告への個別のコメントもありました。
上述したように洋上風力発電という対象は、環境社会学が依拠する立場の一つである生活環境主義の表明では解けない問題群であり、陸上風力発電のように加害-被害の構図を容易に設定することはできないといえます。コメンテーターのコメントにもありましたが、環境社会学の議論はほぼ消費されており、自然科学や政策科学が環境社会学の議論を解像度の高低はあるにしたとしても、ほぼ飲み込まれている(洋上風力発電の調査でも同様な傾向がある)状況です。ちなみに筆者は避難者支援の分野で災害研究も行っていますが、地域社会学の災害研究の視点は、すでに都市計画や社会工学の災害研究でも獲得されていると思われます。社会学の視座がスピード感が早い学問領域に取り込まれた時、社会学内に閉じこもるという対応もありますが(当然、学問的には縮小再生産になるでしょう)、そのような志向性は「環境社会学らしくない」と考えます。
しかも、2050年までのカーボンニュートラル、生物多様性における30by30といった喫緊の課題がある中で、社会学(人文学も同様)の「そもそも論」や「批判」は、現実をスピーディーに理解する実学系からはスルーされることでしょう。このような状況の中で、環境社会学ができることは、事例対象との「伴走型研究」、現実のスピード感と「丁寧さ」を両立させるようなガバナンスをデザインする役割、すでに構築されたシステムや事業に対して「いったん立ち止まる」などの介入や、その介入方法をデザインすることを考えていくといった内容が議論されました。従来の社会学者の役割とは全く異なるし、クラシカルな社会学者には理解されないのではないかと思いますが、こうした研究スタイルは環境社会学だけではなく、別の領域でも胎動していると思います。
さて、フロアーからは洋上風力発電の議論をする上で、漁業や漁業権の話をより詳細に調査、分析するべきではないかという意見が複数寄せられました。これに対しては、環境社会学の中で従来、議論されてきたコモンズ論と接続させつつ、洋上風力発電開発と既存のコモンズとの関係を調査分析するだけではなく、再生可能エネルギーの地域貢献策を通じて、多様な自然資源と地域の「コモンズ」とするための社会的仕組み等を考えていく必要があると思われます。
今回の企画セッションは、共同研究者によるゼミ(演習)のような様態であり、「学会を私的に利用した」と訝しがる会員もいたかもしれません。その点については企画セッションの冒頭でお詫びしたのですが、一方で、企画セッションは一会員が、研究活動委員会とは別に、企画(パネル)を作ることができる唯一の機会です。会員としての「権利」を行使させていただいたわけですが、会員による企画セッションの応募が本企画だけだったことに危機感を覚えました。もっとも、個人的には報告を通じて調査研究の整理が少しずつですが進行し、多様な方からいろいろな意見を伺えたことに感謝する次第です。ありがとうございました。
自由報告部会A「公害・環境汚染と市民運動」報告
堀田恭子(立正大学)
本部会「公害・環境汚染と市民運動」では、5本の報告があった。一番目の湯浅報告は「素材型モノ研究の視点からのプラスチック研究」であった。これまでのモノ研究を手掛かりに、素材としてのプラスチックに着目し、原料段階から、生産、消費、リサイクル、廃棄というライフサイクルを追いかけることで、プラスチックが持つ有害性や、ゴミとリサイクル、海洋汚染等多様な問題との関連付けを捉えようとした報告であった。そのためにまずプラスチックをめぐる社会意識に関する調査分析の報告が主となった。フロアからは、年代に注目したときに、プラスチックに関する情報や学校教育の視点、地域の違い、ジェンダー差の有無等が質問された。他方、プラスチックの製造過程において、アセチレンからナフサに移ってきたことに関する言及も、問題群と関連させる際に必要なことではないかというコメントも出された。
二番目と三番目は「有機フッ素化合物(PFAS)汚染問題の多元的問題枠組みと市民運動」と題して、まず寺田報告の副題は「運動体間の連携形成とフレーミングの多様性」でPFAS汚染の問題点・事件史を日米から紐解き、最後に問題フレームの類型を提示した。PFAS汚染そのものに関する日米並びに諸外国における違いに関する質問や、四つのフレーム類型(反軍事基地運動型、地下水源による持続可能な「水源自立」維持フレーム、産業公害・労災問題フレーム、ストック公害リスクフレーム)による解決の違いの有無、さらに原因確定の難しさからの運動の困難、運動と市民科学の連携など、フロアの議論は多方面に渡った。続く三番目の木村報告の副題は「日本における産業公害と米国NGOによる“市場的な論理”を活用した運動の分析」であり、生産の踏み車モデルとエコロジカル近代化フレームを用い、米国のNGOによる株主提案を活用した運動と、実際の効果の提示をした。さらに摂津市と多摩地域におけるPFAS対策への運動の実態も明らかにした。米国での上記の運動が、日本においてどれだけ有効かは未知数ではあるが、市場の論理を軸にして、フロアからは運動の海外連携の有無、PFASにおける疫学調査の現状、市場論理の逆利用への疑問などが挙げられた。
四番目の友澤報告は「石炭鉱害の問題構造―九州北部の資料調査からの検討」であった。今まで中心的課題として取り上げられてこなかった石炭鉱害において改めて資料調査をもとに、問題構造の把握を試みたものであった。石炭鉱害は社会問題化し、法制度等ある程度結実したため、トピック化されてこなかったという理由はあるが、改めて九州北部における鉱害の記録を紐解くと、福岡県は体系的に資料が存在するものの、長崎県においては断片的であり、さらに全体的に戦後の復旧事業に関する資料が少ないことがわかった。そこから地域産業としての農業との関係性、水資源も絡んだ鉱害被害への地域住民の動き等、限定的ではあるが、資料から抽出し提示した。フロアからはじん肺の取り扱いや、情報という観点から見た地域差の問題、また識字率と住民の動きとの関係、報告者が提示した無過失責任との関係から原賠法との関連性の指摘もあった。
最後の原田報告は「胎児性水俣病世代の社会的被害―ある女性のライフヒストリー」であった。1955年生まれの調査対象者は、胎児性水俣病世代と同世代でありながら、自分は水俣病患者であるとは気づかず、周りもそう規定せずに数々の困難を抱えながらも「健常者」として生きてきた。2000年代に入り初めて診察を受け、翌年申請したが棄却された。現在は、原告の一人として裁判に加わっているが、訴訟に勝って国に「水俣病患者」として認めさせるというよりも「記録」として残すことが重要だとして運動を行なっている。構音障害や能力のアンバランスの原因の一端が水俣病でと結びつけられていないという水俣病が持つ社会的被害の不可視化が対象者のライフヒストリーから明らかにされた。フロアからは、水俣病患者であるという自覚の経緯や、結婚、出産等における不安の有無、家族の裁判状況等と対象者の運動の関係等が質問された。
今回の5報告は、戦前からの鉱害問題、戦後の公害問題(水俣病)、さらにそれと並行する形での石炭から石油使用と製造工程が変わったプラスチックの存在、そして有害化学物質としての有機フッ素化合物(PFAS等)の問題の顕在化という大きな時間軸の中で、個別的断片的な問題群として捉えられるべきではないだろう。確かに時代における社会構造的な違いはあるが、日本社会という社会構造の大枠の中では、連続性をもつものとして捉えられるのではないだろうか。それら一連の流れの中で運動という社会学のオリジナルな視点を取り入れ、市民科学、科学技術社会論等の知見を加えていくことで、個別の研究がより豊富化されるのではないかと感じた。
自由報告・実践報告部会B「地域課題解決に向けた保護・保全」報告
廣本由香(福島大学)
部会Bは、自由報告3件と実践報告2件の混合部会であった。人口減少や過疎化が深刻な農山村の自然資源をどのように保全・保護し、地域の持続可能性を築いていくのか。あるいは、現在の制度や施策にどういった課題があり、それを乗り越えるためにも、どのような仕組みや連携が必要であるのかを、司会とフロアとともに考える部会であった。
第一報告は広島大学大学院の中島佑輔氏による「“オオサンショウウオ”の保護を如何に伝えるか」であった。鳥取県内の堰堤を例にあげながら、公的なオオサンショウウオの保護の物語において、保護と相反する人間の活動という区分けがどのような過程で生じているのかを報告した。フロアからは、昨今のオオサンショウウオをめぐる保全状況の変更や、グレーバーやラトゥールの理論を本研究に導入する意義などの質問があがった。
第二報告は東京大学大学院の岸野奏氏による「主伐・再造林問題を克服する地域社会の対応―長野県佐久地域のカラマツ林業を事例に―」であった。長野県佐久地域の事例から、主伐再造林問題と地域林業の社会関係や意思決定、森林組合と民間事業体が取り組むべき課題、地域林業が向き合う木材市場について報告した。林業を専門としないフロアのために、司会からは前提となる林業政策やカラマツの特性などの補足説明があり、フロアからは地域林業の事業体の実態やローカルネットワークに対する質問があがった。
第三報告は京都大学大学院の山村哲史氏による「棚田での共同作業を通じた保全意識の共有プロセス分析―京都府福知山市の棚田オーナー制度を対象として―」であった。毛原棚田を事例に、棚田オーナーと住民へのアンケート調査の結果を踏まえた上で、棚田オーナー活動を「実践コミュニティ」の観点から分析し、インタビュー調査からも棚田オーナーの活動の意識変化を明らかにした。報告では、棚田オーナーは継続な活動を通じて、どの程度、住民と保全意識を共有できるのかという問いから、定住者でない棚田オーナーが「一筋縄ではいかないこと」へ理解・共感することの重要性について言及した。
第四報告(実践報告)は、名古屋大学大学院の紀平真理子氏による「地域課題解決を目指す学際的教育プログラムの実践と課題―人材育成と地域貢献の間で―」であった。報告者が所属する大学の課題発見・提案型プロジェクトへの参加を通じて、教育プログラムと地域協働から明らかになった、①プログラムのゴール設定の明確化、②学際的プログラムでのインフォーマルな場の設定方法、③定量的提案に住民の意見や視点の組み込む方法の検討の必要性を、学生の立場から報告した。また、教育プログラムが地域に与える影響や持続可能な関わり方を考慮する必要性が問われた。
第五報告(実践報告)は、 大和大学の天野健作氏・立花晃氏による「SDGs を足元から―学生プロジェクトを世界へ」であった。報告者が代表を務めるSDGSプロジェクトと株式会社ヴェリダスの設立、他の企業・団体と連携しながら進めている事業について紹介した。具体的には、賞味期限が近いチョコレートの販売を通してフードロスの実態や削減を訴えたり、煮干しや玉ねぎなど市場には出回らない地場産の食材を使った「すいたぶるラーメン」から「まちおこし」や日本文化の発信を学生とともに精力的に進めていることを報告した。
いずれの報告も、問題意識や課題感は根底で通じており、急速に変化する環境への適応のほか、誰が地域資源を守り、創り、社会に発信していくのかが問われているように思えた。
自由報告・実践報告部会C「環境問題をめぐる意識・政策・支援」報告
三上直之(名古屋大学)
部会C「環境問題をめぐる意識・政策・支援」では、都市や地域における気候変動対策、若年層の環境意識の国際比較、エコロジー的近代化論の再検討を主題とした4本の自由報告が行われた。司会者として4報告を聞いた立場から、各報告の要点を紹介しつつ、質疑応答も踏まえての印象を述べることで部会のレポートとしたい。
第一報告・佐々木晶子氏(日本貿易振興機構アジア経済研究所)の「質的データ分析(QDA)を用いた国際都市ネットワークと気候正義に関する分析と考察」は、気候変動対策に関する4つの国際都市ネットワークの公式文書における「気候正義」への言及の変遷を分析し、その変化が都市の気候正義に対して持つ意味を明らかにすることを試みた。文書の内容分析の結果、C40(世界大都市気候先導グループ)のように、2019年以降、「正義」という語の使用が顕著に増えているケースがある一方、公開文書における気候正義への言及がほとんどないネットワークもあった。今回は、政策文書へのキーワードの出現頻度から大まかな傾向をつかむ導入的な研究の報告だったが、報告者らは今後、ネットワーク組織や加盟都市、その他の関係諸主体による意思形成のプロセスを解明するためインタビュー調査を予定しているという。それを通じて今回示された変化の背後にある過程が明らかにされれば、環境社会学の研究として、報告者らの当初の狙いに迫る深まりにつながる可能性があると感じた。
第二報告・平岡俊一氏(滋賀県立大学)の「日本の地域脱炭素分野における中間支援体制の整備に向けた論点・課題」は、「地域脱炭素」の政策が国内でも活発化する中、欧州ではエネルギーエージェンシーのような地域密着型で専門性の高い組織が担っている中間支援の機能を、日本ではどのように整えることができるかを検討した。研究方法として、国内でこの分野の中間支援活動をすでに行っている関係者らを集めたワークショップを開き、その場で実際に出された意見をもとに論点・課題を洗い出した。その結果、少数の地域地球温暖化防止活動推進センターや、環境NPO、地域エネルギー会社、研究者・研究機関が、「身を削りながら」各地で地域脱炭素の取り組みへの支援を行ってきた現状が明らかになった。報告では、複数組織からなるコンソーシアム型の支援体制の構築が提言され、資金源や中立性の担保、国や自治体との関係性といった課題が指摘されていた。地域脱炭素をめぐっては現場での動きが速く、本報告も状況に機敏に即応した実践的な研究であると感じた。今後の展開に即した、さらなる研究に注目したい。
第三報告・王子常氏(龍谷大学)の「若年層の環境意識の実態とその影響要因―日中比較を通して―」は、日本の大学生を対象とした質問票調査と、中国の大学生へのインタビュー調査をもとに、日中の若年層の環境意識とそれを規定する要因を探った。両国における既存の意識調査も踏まえ、「現在志向」「脱物質主義」「権威主義」「親密圏没入」の4要素が、環境意識への影響を与える要因であるとの仮説を設定。日本の大学生調査では「脱物質主義」の影響が最も強く現れ、「権威主義」や「親密圏没入」とも有意な相関が見られたが、中国では「脱物質主義」と環境意識との間で有意な相関は見られなかったという。中国の大学生への聞き取りによれば、環境問題への関心や知識はあるが、進学競争の厳しさなどから積極的に関与する余裕がない現状がみられ、これは日本における「親密圏没入」と類似性があるとの考察が示された。本報告では解析結果の詳細までは示されておらず、今回報告されたのは暫定的な知見と思われる。今後の研究で、日中の若者の環境意識の共通点と相違点について、さらに解明されることが期待される。
第四報告・佐藤圭一氏(一橋大学)の「エコロジー的近代化論再訪―ノーマル化された時代における挑戦―」は、環境政策の理念として国際的に広く受け入れられるに至ったエコロジー的近代化論(EMT)について、1970年代の源流にまでさかのぼって、その展開をレビューした。特に最近の動向も踏まえると、すでにそれ自体が主流の言説となったEMTをめぐっては、「強いvs. 弱いEM」や、西欧とは異なる東アジアの「圧縮された近代」におけるEM、経済成長と環境汚染の完全なデカップリングを目指すEM2.0など、EMT内部での違いを精緻に捉えることが重要だという。とりわけEM2.0の議論には、デカップリングを徹底するため、ジオエンジニアリング(地球工学)などの大規模・高リスクな技術の導入が組み込まれている。報告者が、従来型ではないEMTについて「さまざまな角度から構想・分析していくことが環境社会学における今日的課題となっている」と結んでいた通り、最近のEMTの議論を批判的に読み解くことで、環境問題の解決に向けた研究・実践への豊富な示唆が得られるのではないかと感じる報告だった。
大会印象記(岡田美穂)
岡田美穂(名古屋大学大学院)
私は大会2日目の「部会B 地域課題解決に向けた保護・保全」と「企画セッション 脱炭素に関わるドミナントストーリーと環境社会学―洋上風力発電を事例に―」の発表部分、「部会C 環境問題をめぐる意識・政策・支援」の後半に参加しました。簡単にではありますが、以下に感想を書きたいと思います。
部会B前半の自由報告は、治山・治水や林業、農業の地域課題が対象でした。質疑を通じて、地域の自然を踏まえた生活や産業の成立過程、さらには世界動向も含めた課題の背景への理解が深まり、地域の課題を自身の問題関心に引き付けて考えることができました。後半は、大学の講義等の場における実践報告だったため、実務に関わる質疑や反響が先生方から多数あったのが印象的でした。これらの報告は、地域課題解決を大学の教材としてどう扱うか、という議論のきっかけとなるのではないかと感じました。
企画セッションについては、洋上風力という、国内で今後本格化する社会的関心事がテーマでした。今後も事業者決定、建設、運転の各段階で継続的に企画し、ドミナントストーリーの変化を追っていくと面白いのではないかと思いながら聞いていました。
部会Cは、最後の発表しか聞けなかったのですが、エコロジー的近代化論の歴史から最近の動向までが網羅された非常に濃い内容でした。質疑の中では、部会Aにおける発表と関連して、エコロジー的近代化論の発展の中でリスクへの懸念のようなものが薄まっているのではないか、という意見もありました。このような現実の問題と関連付けた建設的な議論を聞くことができたのも、大変有意義でした。
最後になりますが、発表や大会運営に関わられた方に感謝申し上げます。
大会印象記(岸本華果)
岸本華果
新卒から2年間働いた会社を先月退職し、博士課程進学を検討している中で、今回初めて環境社会学会に参加させていただいた。
- 地域社会における軍事化の浸透と抗いの可能性
- 地域課題解決に向けた保護・保全
- 脱炭素に関わるドミナントストーリーと環境社会学―洋上風力発電を事例に―
を聴いた。
国防については国と地方の権限に差があり、意思決定に住民が参加できない。急に外から話がやってきて、反対しないと賛成していると解釈されてしまうため、抗ったところでとめられるかはわからないが、抗わざるを得ない。ずっと抵抗し続けないといけない。“脱軍事化”はどのようにして可能か。自分のところにさえなければいいという話でもない。ではどうするのか?という話になる。
洋上風力についても同様の話があり、反対運動の後に地域に何が残るのか、気候変動対策はどうするのか、と。
軍事化の方は地理的に「基地が自分たちをまもってくれる」という認識もあるようだが、洋上風力の場合は発電した電気が周辺地域で使われるわけではなく、どちらかというと都市への供給になるというので、そこに難しさがあるような気がした。
いろいろ考えさせられたが、こうして立ち止まって考え、議論できる時間はとても幸せだった。洋上風力のセッションの丸山先生からのコメントにも通じるが、企業や行政の場合は締め切りがあったり、スピード感が全く違ったり、そもそも論を問いにくい状況にある。私自身も企業で働いている時には、明日までに決めて進めないといけないという中では、じっくり考える時間も体力もなく、もやもやを抱えながらもとりあえず進むことを繰り返しているうちに疲弊してしまった。「反省会としての研究ではなく、伴走型の研究」というのはとても共感する。私もそういう形で貢献できるようになりたいと思った。
大会印象記(佐々木晶子)
佐々木晶子(日本貿易振興機構アジア経済研究所)
2024年5月に環境社会学会に入会し、今回初めての大会に参加した。参加する前は、まずはどのような大会なのか出席してみて、様々な研究報告から学ぼう、という気持ちと、ちょうど第一段階の完了した自身の研究活動を報告し、フィードバックを得たいという気持ちの間で揺れていた。だが、コロナ禍で進めてきた研究のため対面で人に発表することがなく、また普段筆者は研究の支援を行う立場にあり、自分の研究報告を行う機会が少ない。結局、恥をかいても発表して、研究内容を見直す機会が欲しい、という思いが勝ち、部会Cにて報告をさせていただいた(第1報告 「質的データ分析(QDA)を用いた国際都市ネットワークと気候正義に関する分析と考察」)。結果として、発表の仕方や研究課題に対する根本的な問いなど、厳しい意見もいただき、研究内容を見つめなおす非常に得難い機会となった。
部会Cをふりかえると、第2報告「日本の地域脱炭素分野における中間支援体制の整備に向けた論点・課題」(平岡俊一氏)では、日本の自治体レベルでの脱炭素化における中間支援組織の体制構築について、欧州との比較および中間支援に関するワークショップ等の取り組みから見えてくる、資金確保や組織の専門性、継続的支援の必要性といった現状の課題について報告がなされた。中間支援組織の重要性は福祉や地域振興といった他分野でも認識されており、特に筆者は以前携わっていた地域振興における中間支援組織づくりとの共通の課題と難しさを感じ、大変興味深く報告を聞いた。
第3報告「若年層の環境意識の実態とその影響要因―日中比較を通して」(王子常氏)では、日本と中国の若者の環境意識の実態とそれを形作る社会的要因に着目し、アンケートやインタビュー調査、文献調査などの結果をもとにした日中比較に関する考察について報告があった。会場からは、環境意識の影響要因の比較方法についてなど質問があった。個人的には、中国の若者の環境意識は年配層に比べて高いが、一方で「内巻(ネイジュエン)」と呼ばれる、近年中国の若者が仕事や学業での苛烈な内部競争に晒され疲弊する社会現象によって、環境問題をはじめ社会問題に目を向ける余裕がなくなっており、日本の若者にも類似の現象がみられるという内容が印象に残った。
第4 報告「エコロジー的近代化論再訪―ノーマル化された時代における挑戦」(佐藤圭一氏)では、エコロジー的近代化論(EMT)の理論的発展の振り返りと内部の類型整理(強いEM、弱いEM、開発主義的EM、EMT2.0)を通じてEMTの限界と今後の発展可能性について議論が行われた。
本部会のみならず、今回大会に参加することで、他の研究報告からもたくさんの学びを得ることができ、2日間、ノートを取る手が止まらなかった。公害や基地問題など長年に渡り取り組まれてきた課題から、最近のPFAS汚染問題まで、今まで教科書的な知識しか持っていなかったテーマもあり、環境社会学的見地から環境と社会の関わりを捉える意義と重要性を教えていただいた。今回学会に参加し、温かく迎えてくださるお声をたくさんの方からかけていただき、感謝の気持ちを感じるとともに、次回報告を行う際は、(少し足がすくむけれど)自信をもって報告できるよう、今後も研究活動に邁進していきたい。