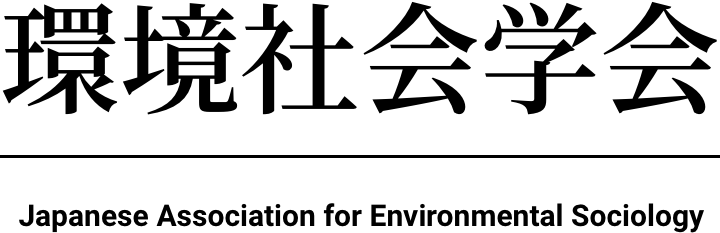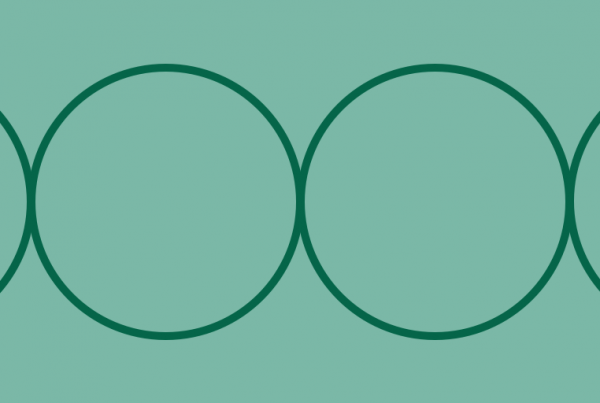環境社会学会は、2023年6月10日~11日に第67回大会を東北学院大学土樋キャンパス他にて開催しました。シンポジウムと自由報告部会の報告を掲載します。
シンポジウム「負の記憶を紡ぐー伝えること、伝わることの困難の先へ」報告
高崎優子(北海道教育大学)
戦争や公害、災害など、経験した人びとの痛みや喪失を伴う「負の記憶」は、それを語ることも、また聞くことも、容易ではない。記憶の起点となる出来事への距離やその解釈は人によって違いがあり、その違いは、出来事を経験した人と経験していない人とのあいだ、そして同じ出来事を経験した人々のあいだにさえ、「隔たり」を生じさせる。
しかし、記憶の伝承が他者とのあいだで立ち上がるコミュニケーション行為であるとすれば、伝承を通じて隔たりを越え、記憶を共に紡いでいくことの可能性、負の記憶が未来への回路となることの可能性を探ることができるのではないか。本シンポジウムは、このような関心のもとに、震災・原発事故特別委員会企画として実施した。当日のプログラムは以下の通りである。
- 趣旨説明:高崎優子(北海道教育大学/震災・原発事故特別委員会副委員長)
- 第一報告:高橋広子(石巻市震災伝承推進室/石巻市震災遺構整備・展示担当学芸員)「わたしたちの記憶を紡ぐ 未来のいのちへつなぐ—石巻市震災遺構と展示が伝えるもの」
- 第二報告:藤間千尋(公益社団法人3.11メモリアルネットワーク理事)「東日本大震災の記憶を伝える—大事なことは沢山の人と」
- 第三報告:椙本歩美(国際教養大学)「負の記憶は伝わるのか—戦争記憶を伝えられた経験から」
- 第四報告:青木聡子(東北大学)「語られる住民運動の『生傷』—『被害』の可視化、そしてその先の可能性」
- ディスカッション・会場との質疑応答(司会:高崎優子)
第一報告の高橋氏からは、自身の被災体験にも触れながら、震災遺構の展示のコンセプトの説明と、来館者の反応が報告された。コンセプトは「どう残すかではなく、未来へ何を伝えたいかを問う」という視点のもとに練り、展示は来場者への「問いかけ」を重視して制作したとのことである。話し合うこと、考えること、ともに確かめ合うことで、あるべき未来が続いていくはずだ、というのが高橋氏からの投げかけであった。
第二報告の藤間氏からは、被災者が伝承活動に関わる全てを担うのは負担が大きすぎる、という現場での気づきから、被災当事者ではない人びとが伝承活動を行う「語り継ぎ」に取り組んでいることが報告された。聞き手からは概ね好意的な評価を得ているとのことである。藤間氏の指摘は、出来事の風化に対し、伝承活動の「関わりしろ」を見つけ、伸ばしていくことの重要性であった。
第三報告の椙本氏からは、戦争記憶をめぐり、それを聞く側の戸惑いや困惑が率直に示された。その困惑の中で見出されたのは、記憶の継承が、必ずしも出来事の全面的理解を要するものではないということである。記憶をめぐり人びとが関わり合うこと自体が伝承であり、時間の経過とともに「受け止め」が変化していく可能性があり、記憶の多義性を保持することが記憶を周縁化しないために重要であること、そして、多義的で両極的な個別の語りから総体を想像する力が必要であることが示された。
第四報告の青木氏からは、芦浜原発反対運動をめぐり、運動の「痛み」やネガティブな部分が公に語られることについて報告がなされた。青木氏によれば、それらはじつは原発建設をめぐってコミュニティが瓦解したという被害の語りであり、ひいては瓦解をもたらした電力企業の加害の告発である。いまだ「生傷」である被害を語り続ける行為は、地域社会全体が被害者であることの社会的承認に向けた行為であり、そこに地域社会の亀裂の修復への展望可能性が見出されるという指摘がなされた。また、修復に向けた第三者の介在の必要性について、研究者がその役割を担う可能性があることも示された。
フロアからは、「語り継ぎは何を残し、何を失わせるのか」「(行政である)高橋氏と(民間である)藤間氏はお互いの存在をどのように捉えていたのか」「加害の告発はコミュニティの対立を深めることにならないのか」などの質問が寄せられ、質問に答える形で、報告者間で活発な議論が交わされた。「語り部活動の当事者として、語る場、語ってよい場が生み出されたことに大きな意義を感じている」、「地域社会の『幸せな記憶』もまた伝えられていくことに大きな希望を持っている」といったコメントが寄せられたことは、本シンポジウムが、未来への回路を少しでも示し得たのではないかと希望を持った。
一方で、「個別の語りから総体を想像する力はどうしたら得られるのか」という質問があったように、伝承というコミュニケーション行為が成立するには、まだ多くの考えるべき論点が残されている。公害研究を嚆矢とし、被害という磁場のもとに議論を重ねてきた環境社会学にとって、今後も継続が求められる議論であるだろう。4名の報告者、そして多くの質問を下さったフロアの皆さまに深く感謝を申し上げたい。
最後に、今回大会はシンポジウムを初日に、エクスカーションを二日目に行うという、従来とは異なる日程で実施された。報告を先とすることで、エクスカーションに参加される方々の理解の深まりの一助となれば、という意図からである。その意図が果たされていれば、大変幸いに思う。
自由報告部会A「災害/リスクをめぐる経験と実践」報告
関礼子(立教大学)
本部会では、原子力発電所に関する災害/リスクに照準をあてた4つの報告があった。
第1報告は、佐藤重吾氏の「福島県の放射能汚染被害地域における山菜の流通管理レジーム――『野生』と『栽培』、その『あわい』に着目して」である。原発事故後に森林から産出される「野生植物」に着目した環境社会学研究としては、金子祥之論文(『環境社会学研究』№21所収)や山本信次論文(同№25所収)が思い浮かぶが、本報告は山菜を「野生」と「栽培」に分けて、「栽培」ベースで原発事故対応の山菜出荷レジームを構想しようとするものである。環境や栽培プロセスの管理などを通して、市町村管理の出荷停止を回避する動きを推進しようという「知恵」は、被害地域にとって有益であるに違いない。問題は「あわい」をどう捉えるかだろう。
第2報告は、東城由佳理氏の「原子力災害被災地域出身の若年女性が地元に帰る/帰らない理由――福島県楢葉町を事例として」である。避難指示区域であった自治体の居住人口の性比は明らかに男性に偏っているが(『シリーズ環境社会学講座3』所収の藤川賢論文)、東城報告は25~29歳の女性割合が3割以下の楢葉町に注目し、なぜ帰るのか、帰らないのかを8名のインタビュー調査をもとに考察し、被災地特有の「負い目」や責任感を感じることが「責任の個人化」になっていると指摘する。ただし、ここにジェンダー差がどう関係するかは今後の課題として残された。
第3報告は、除本理史氏による「『困難な過去』の継承を担う民間施設の意義と役割――福島原発事故を事例として」であった(林美帆氏との共同報告)。公害など「困難な過去」のヘリテージ化に多視点性を持ち込む必要性を論じつつ、いわき市の湯本温泉・古滝屋の「原子力災害考証館」と、楢葉町の宝鏡寺の「伝言館」の事例が紹介された。民間施設は多視点からの教訓と継承に果たす役割が大きいが、施設を持続させていくうえで制約があるという指摘は、翻って公的施設の「壁」を意識させる。それをプライベートとパブリックとの役割分担と捉えるべきか、それともパブリックがパブリックとして機能していないと捉えるべきか、考えさせられた。
第4報告は、高野聡氏の「核ゴミ最終処分場の文献調査が進む北海道寿都町でのアクションリサーチ」である。報告では、町長が応募した高レベル核廃棄物最終処分の文献調査応募から2年半の状況と、アクションリサーチを通した町民のエンパワーメントについての報告があった。NUMOの「対話の場」の分析から、対話の理念が遵守されていないため、対話が分断を大きくしている状況も示された。対話の場の構造が合意か対立かを規定すると捉えたときに、多くの示唆を含む報告であった。
部会Aは、同時並行で開催された部会Bと比べて報告数が少なく時間的にゆとりがあり、かつまたテーマが相互に関連していることから、4報告が終わったところで総合討論の時間を設けた。フロアーからの感想・意見・コメント、そこへの報告者の応答と、議論するに時間が長すぎるということはなかった。かつて「朝まで討論会」などという「伝統」があったのだ、と思い出しながら、司会者としても議論を興味深く聞かせていただいた。特に、「実践報告」である第4報告に対し、寿都町の状況を詳細に把握したいというフロアーからの質問が印象的であった。環境社会学会にとっての「実践報告」の重要性が示されたのではないかと思う。
自由報告部会B「自然/環境をめぐる認識と実践」報告
茅野恒秀(信州大学)
部会B「自然/環境をめぐる認識と実践」では6本の報告が行われた。近年の環境社会学の裾野の広がりゆえか、部会テーマは包括的で、また総合討論の時間を確保することも叶わなかったため、ここでは6本それぞれの内容と議論を紹介することで、学会員の皆様への報告に替えさせていただく。
笹岡・佐野報告は、カリマンタン島中央部のM村における「機械化された小規模金採掘(MSGM)」の広がりを受け、より持続可能性の高い小規模金採掘の可能性を探究するために、M村でのMSGMの営みを子細に把握し、村人が望む開発のあり方を把握しようとする試みである。事例のディテールが存分に説明されたため、会場からの質問も具体的で今後の研究の展開にそのまま援用可能なコメントも多かった。筆者もとくに知りたいと思ったのは、M村ではこれまでにも外部からの地域開発の提案に対して村として民主的な意志決定を下してきたという文脈で、これが村人の“MSGMを慣習法組織が制御することが望ましい”とする選択にどのように作用しているか、という点であった。その意味で、開発シナリオを専門家が5つの選択肢として提示するよりは、むしろゼロベースで対話を重ねるアクションリサーチの可能性もあったのかもしれない。今後の展開が楽しみである。
著名な林業地帯である大分県日田において、生産森林組合や財産区などの共有林が上下流連携のフィールドに活用されることで価値の今日的転換が生じていると論じた佐藤・吉野報告は、私有林より共有林のほうが公益的事業と親和性があり、当地では災害の経験が水源機能の保全などの価値を住民に認識させるに至ったとの仮説的結論が示された。これに対して、当地の文脈を詳しく知る聴衆から2つの大きな指摘があった。第1に、当地の共有林経営が不振に陥っているとの前提は、原木シイタケなどの無視できない経営規模を考えれば一面的な見方ではないか、第2に日田が有する筑後川源流域としての位置づけや下筌ダム(「蜂の巣城闘争」の現場)等の経験をふまえるべきではないか、との指摘である。これらは、地域や生業は複層的なスケールで捉えられるという環境社会学が積み重ねた知識基盤に基づく指摘であり、今後の研究を進める上で大きな示唆となったのではないかと期待したい。
福井県三方五湖で長年フィールドワークを展開する富田氏による報告は、環境ガバナンスを支える主体のエンパワーメントに、学びがどのように寄与しうるかという問題関心から、アクションリサーチを通じて、学びと学びの場の可能性と、困難性とを浮き彫りにするものであった。質疑応答では、実践上の障壁となる構造的課題に議論が集中したが、筆者のみるところ、さらに意味ある実践につなげるためには学びの内実や質についての考察をより深める必要があると思われた。報告者が近年、継承が明確に断絶し始めたと危機感を募らせる時代においては、常に「生産」「生活」のために人が自然とかかわる必然性があった。自然にかかわることと自然の応答(痛みや破壊を含む)とがセットで経験される生産・生活を通じた学びは、学校が設定する「めあて」やカリキュラムとは質を異にする体系性が本来的に備わっていたのではないか。つまり、「自然とのかかわり」とは何かが、根源で問われている。
野口報告は、今後進められる研究プロジェクトの立ち上げに際した報告という性格もあり、諸構成要素がまだ全体構成の中に安定できていないところが否めなかった。ただ、報告者が示した検討の方向性は、環境社会学における順応的ガバナンスや気候民主主義などの議論を通じて提示される諸論点と密接にかかわり、その知識基盤を丹念に吸収することで進展が期待されよう。今後、気候変動適応策や緩和策が実行に移されると、居住地を含む生活環境を根本から転換すべしと”客観的に”評価される地域や層において”意図的社会変動”が生じることになるが、報告者の「科学的知見や地域開発のアイディアをもってくる専門家と、先住民族や地域の人びとが対話し協働することが不可欠」とのモデルがまったく無力化してしまう状況も生じうる。そうした中では、報告者が言う「守られるべき対象層」が、誰によって、どのように構築されているのかを絶えず問い直す必要もあるだろう。
アイヌの自然とのかかわり、またアイヌそのものが漫画にどのように表象されているかを丹念に読み解いた山口報告では、野田サトルの『ゴールデンカムイ』が、手塚治虫の『シュマリ』に典型的に表れる”自然との共生”という画一的な像を乗り越え、自然に働きかけることでときに破壊者ともなるような多様な実像を描くことでポストコロニアルな存在論的表象の領域に踏みこんでいるとの見解が示された。質疑応答ではアイヌの語られ方の変化や、従来あったタブー性についての指摘があったが、筆者からもう1つ視点を加えさせていただくとすれば、報告者が紹介した野田の「専門家にこまめに確認し、間違いがあれば全力で謝って単行本で修正する」という姿勢にみるような創作戦略の違い、そしてそれを規定する情報社会というべき社会構造の変化をどう見るかという点がある。これは脱構造の視点に立つとした報告者の立場が明確であるがゆえに、気になった点でもあった。
張報告は、世界価値観調査の中国における調査結果をシュワルツの価値観指標を独立変数に分析したものであった。①経済成長率の低下、失業の増加があっても環境保護を優先すべき、②環境が悪化しても経済成長と雇用創出が最優先されるべき、との2つの見解に対する価値観の影響を推論し、2007年と2013年の2時点では自己志向(Self-direction)の価値観を有する人が①環境重視→②経済重視の考えを有するようになり、刺激(Stimulation)を有する人では②経済重視→①環境重視の変化がみられたと結論づけた。各価値観と社会階層の関係などの前提情報が十分に示されなかったため、会場からの質疑も“推論”に頼らざるをえなかったが、この変化の要因として報告者からは2008年の北京五輪に伴う莫大なインフラ投資の後、経済の冷え込みがあったため、2013年の時点で自己志向の価値観保有者が経済重視の考え方へシフトしたとの仮説が示された。この仮説については、より丹念な検証が必要と思われた。
本部会では、環境社会学の知識基盤から得られる認識を手に、フィールドでの実践に飛び立っている/飛び立とうとしている報告が目立った。アクションリサーチやシナリオ提示、政策分析評価など実践の文脈は微妙に異なるけれども、堅牢でありつつ、順応的である環境社会学的認識をいかに持ち、実践へと飛び立つかが、共通の課題として問われていたように考える。