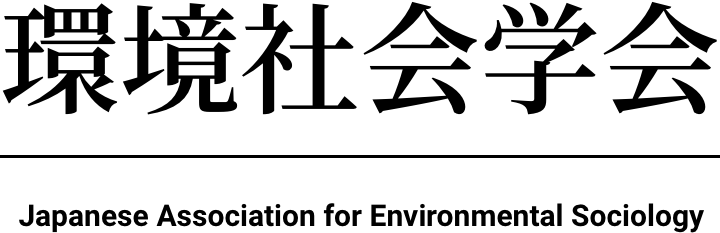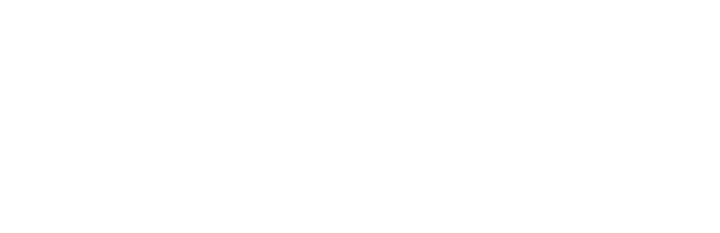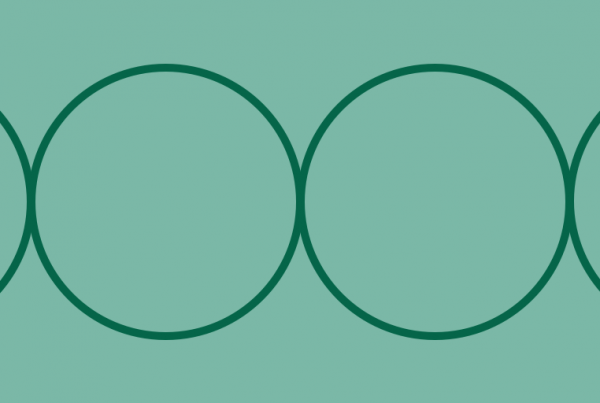環境社会学会は、2024年11月23日~24日に第70回大会を沖縄県立看護大学にて開催しました。部会(自由報告・実践報告)の報告および印象記を掲載します。
大会シンポジウム「環境社会学から問う島嶼の軍事化-沖縄、グアム、マーシャル諸島」報告
朝井志歩(愛媛大学)
現在、沖縄を中心とする南西諸島で、新たな基地建設が民意を顧みることなく進められており、政府はこうした政策を、中国脅威論や「台湾有事は日本有事」といった言説によって正当化している。そして中央政府に協調的な立場をとる自治体の首長らが、国防への貢献を通して政府との関係を構築し、貢献の対価としての交付金を受領して市民サービスの拡充を図ろうとする動きも顕在化している。
この一連の事象を捉えるために、エンローによる、「軍事化」を物理的な軍事施設の建設だけでなく、文化や価値観の変容まで視野に入れて捉える議論は、軍事が社会にもたらす被害を、より広く、深く捕捉することを可能にしてくれる。そして環境社会学もまた、環境の変容からもたらされる被害を、当事者の生活全般に及ぶ社会的側面から捉える視覚を持っており、エンローの視点と重なり合うところが大きい。加えて環境社会学は、意思決定の力関係の非対称性に着目することで、特定の人びとに被害が集中する社会的メカニズムを描き出してもきた。
エンローと環境社会学の視覚を交差させることで見えてくるのは、軍事基地をめぐる様々な事象を通して沖縄が経験していることは、周辺であり、辺境であり、そして先端でもあるという島嶼地域で進展する軍事化がもたらしてきた被害だということである。であるならば、同じように軍事化の被害を受けている、太平洋の島々の経験を共有することは、単なる学問的な関心を超え、社会の脱軍事化を実現するための示唆を得ることにもつながるはずだ。
このような認識のもと、本シンポジウムは、米軍と対峙し続けてきた沖縄を入口に、グアム、マーシャル諸島などの太平洋諸島の島々と結び、島嶼の視点から軍事化を捉え返し、軍事化が島嶼に及ぼす被害と、島嶼に軍事基地を立地させる加害構造を3つの報告をもとに検討した。軍事化が進む島嶼の共通する課題を析出すると共に、軍事化にどう抗うのか、連帯を生み出す可能性について考える場となった。当日のプログラムは以下の通りである。
〇趣旨説明 朝井志歩
〇第一報告 熊本博之(明星大学)「普天間基地移設問題とは何だったのか-辺野古の28年を振り返る」
〇第二報告 長島怜央(東京成徳大学)「「基地の島」の誕生-グアムの戦後復興をめぐって」
〇第三報告 竹峰誠一郎(明星大学)「核開発に抗う太平洋諸島-マーシャル諸島、北マリアナ諸島、フィジーの現地調査を踏まえて」
〇コメント 石垣綾音(株式会社さびら)、茅野恒秀(信州大学)
〇全体のディスカッション
第1報告で熊本は、普天間基地移設問題の経緯を辺野古住民の観点から明らかにし、政府がどのようにして沖縄の抵抗を削いでいき、沖縄に何をもたらしてきたのかを示した。「振興事業・交付金の報奨金化」と「決定権限なき決定者」という2つの点に着目し、辺野古住民・名護市民・沖縄県民が反対の意思を示しても認めてもらえず、賛成したときだけ決定したとみなされるため、そこに報奨金化された交付金が加わると、賛成へのインセンティブが働くことを考察した。さらに、報告者が2022年に実施した沖縄県民意識調査の結果を分析し、「辺野古移設反対の退潮」が起きているとはいえないことや、普天間の危険性の除去につながるとは思えないものの辺野古移設には賛成、ないし「どちらともいえない」という「葛藤あり層」が 3 割いることなどを提示した。そして最後に、本土の人たちの多くは、沖縄の人たちの悩みや葛藤をよく知らないまま、無意識に政府を支えてしまっているともいえることを指摘し、沖縄の葛藤に向き合う必要性を主張した。
第2報告の長島は、地上戦による島の破壊や、米軍による土地の接収と住民の強制移転によるグアム島での米軍基地建設の経緯を説明し、戦後の⽶軍基地建設が、⽶軍側がインフラや公衆衛生、教育、経済などの近代化(アメリカ化)をアピールすることによる「復興」の開発⾔説によって正当化されていったことを指摘した。そして、これらの言説を疑問視した人類学者や現地の人々の意見を無視した形で「復興」が進められたことを示した。また、グアムの基地建設は沖縄で繰り返されたことから、米軍による基地建設や軍事化の「手法」が見えてくるのではないかと提起し、最後に、2000年代後半以降のグアムでの、沖縄からの海兵隊移転に対する住民の反対運動についても紹介した。
第3報告の竹峰は、マーシャル諸島、グアム、北マリアナ諸島、フィジーの現地調査を踏まえ、大国による核実験によって「核の海」とされた太平洋諸島の人びとは、核問題をどう捉え、いかに核開発に抗ってきたのかを明らかにした。1954年のマーシャル諸島発国連請願や、フィジーでの非核太平洋独立運動の誕生、非核独立太平洋会議によるロンゲラップ環礁とのつながりや、集団移住へのグリーンピースの支援、南太平洋非核地帯条約の誕生などの歴史的な経緯が説明された。そして、植民地主義が引き起こした問題として、核問題を人権問題や気候変動問題と交差させることで世界に訴えていく現在の活動が紹介された。最後に、核に抗う太平洋諸島の実践を、沖縄がかかえる軍事問題に引きつけ、言説空間の脱軍事化の必要性や、環境問題として基地を捉えること、つながれる可能性を探ることなどを主張した。
3つの報告に対して、2名の討論者からコメントがあった。討論者の石垣からは、沖縄の住民の立場から、第1報告の熊本が示した「振興事業・交付金の報奨金化」に対して、報奨は金だけではないのではないか、文化的に外から来たものはいいものと評価する風潮や、新しい形での報奨があり、エリートほど取り込まれているのではないか、それが受け入れにつながるのではないかという指摘がされた。また、先住民族問題として沖縄を捉え、脱植民地化の運動として国外では理解されているが、国内ではその理解は難しいのではないかという意見があった。さらに、沖縄の抵抗を削いでいったのは日本政府だけなのか、「決定権限のある非決定者」もいるのでは、という意見が示された。
これらのコメントに対して、報告者からは、グアムでも米兵の増加による特需への期待が住民生活に悪影響を及ぼしている実態について語られた。また、当事者たちのものの見方を解明し、問題を違った視点で捉えることは政治学ではできず、環境社会学が為せることだと示され、太平洋諸島がネットワークを作って抗ってきた経験は、沖縄でもできるのではないかという可能性が提示された。
討論者の茅野は、原子力政策と軍事基地政策には国策として「辺境」を求め、報奨金化した交付金などで立地地域に押し付けていたことに共通性があることを示した。そして、沖縄の基地問題では日本政府も「決定権限なき決定者」として、責任を逃れているのではないかと指摘した。また、「時間の効果」という、その地域にとっては立地された施設が当たり前の存在になることという概念を提示し、時間軸を見る可能性を示した。さらに、第2報告の長島に対して、観光産業は一過性があり、最前線性が求められるため、暴力性を内包しているのではないかと提起した。
これらのコメントに対して、報告者からは、基地を造り続ける限り、交付金が下りてくることへの期待も実態としてあることや、グアムでは軍のためにインフラが整備されていき、それが観光につながった歴史があるため、暴力性が軍によって覆い隠されていくことが語られた。また、未来の可能性の危機という抑止力の問題なのかを問い、現在の問題であり、違った言葉で危機を捉え、「軍事」の捉え方を覆していく必要性が示された。
続いてフロアからも質問や意見があった。意思決定をどのようにコントロールがかけられるかが重要であり、その仕組みが欠けているのではないか、制度の変化にどうつなげるのかを考えなければならないことが示された。また、声が届かない人たちがつながる、連帯の必要性が指摘された。
本シンポジウムでの報告に対する討論者やフロアから様々な刺激的な意見を受け、環境社会学の一領域として、軍事による被害や軍事化が進む社会について研究する意味について改めて考えることができた。軍事化に抗うために、環境社会学がなし得ること、環境社会学でなければなし得ないこととは何か、研究会のメンバーや環境社会学会の会員の皆さまと共に問い続けていきたい。
部会A(自由報告・実践報告)「公害・リスク・開発と地域社会」報告
関礼子(立教大学)
本部会は、自由報告と実践報告が混在するものになった。62回大会から新設された実践報告は「実践家・NGO・NPOとの連携を推し進める」ことを目的としていたが、これまでの傾向として、アカデミックからの実践報告のニーズが大きいようである。
第1報告(大塚彩美:自由報告)の「生ごみ分別によるメタン発酵施設導入に関する社会的受容性」では、これまでの生ごみの分別と堆肥化という状況が変化し、生ごみをメタン発酵施設によりエネルギー源利用する動向が生じてきていることが紹介された。メタン発酵施設という新しい技術と施設建設は、どのように社会的に受容されるのか。行政の周知方法や、住民の反応は、地域ごとにさまざまであることが示され、具体的な住民説明会のあり方、生ごみ分別によるメタン発酵が広域的に行われることの是非などについて質疑応答があった。
第2報告(川俣修壽:実践報告)は、「明治神宮外苑再開発の現場から」であった。現在進行形の再開発の問題点(歴史的景観の破壊、公共空間の私企業による独占など多岐にわたる)が指摘され、再開発に反対する動きとして、開発許可取消訴訟など訴訟運動、コモンズの緑を守る全国ネットの動向や、日本イコモスの警告、都や区、開発企業へのアピールなどが示された。フロアーからは、都市の緑(コモンズ)を開発する動きは、国立公園へのホテル誘致のように、公共空間の私化を促すものではないかという、重要な指摘が出された。また、分析フレームの変化を提示することで、問題の論点が明確になるのではないかというアドバイスがあった。
第3報告(林美帆:実践報告)の「倉敷市水島地区における「困難な過去」の学びと戦争遺跡―亀島山地下工場の保全と活用に向けて」では、公害や戦争など「困難な過去」を地域の観光コンテンツ化する動きが紹介された。干拓地に軍需工場が進出してできた街の戦争遺構をいかに解釈するか、行政が戦争遺構保全と活用に消極的なのはなぜか、「困難な過去」を語る文脈の複数性について質疑応答があった。
第4報告(除本理史:実践報告)は、「福島原発事故における民間伝承施設の利用促進に向けて―地元メディアと連携したガイドブックの作成」であった。福島原発事故の民間施設の利活用が国の復興政策一辺倒に釘をさすのではないかという視点が示された。民間施設の資金・人的資源の持続性をめぐり、殊に水俣病の資料館を念頭においた議論が交わされた。予算はあるがコンテンツ集めが困難な官、持続可能な資金調達のための工夫が必要な民という対比が浮かび上がると同時に、報告者からは、官と民を対比するだけでなく、人的ネットワークに注目する必要もあることが語られた。
4つの報告は、いずれも具体的な事例(フィールド)を重視するという点で、環境社会学ならではの報告であった。だからこそ、欲張って、個々のテーマをフロアーと共有し、深めていくための、実践と研究を架橋するような補助線(「問い」や「方法論」)を、求めたいと感じた。
*共同報告では報告者のみの名前を掲げている。
部会B(自由報告)「食をめぐる環境・動物とのかかわり」報告
岩井雪乃(早稲田大学)
第一報告・堀田恭子氏(立正大学)の「台湾油症政策の変遷と『被害』」は、台湾における油症事件に対する政策の特徴を、日本でのカネミ油症事件と比較考察し、台湾では被害者救済につながる法制度が日本よりも進んでいる要因を報告した。フロアからは、発表で指摘された要因(被害者運動の拡大、ドキュメンタリー映画の社会的影響、研究者の深いコミットなど)が生じた背景について質問があり、さらなる台湾と日本の比較が進むことを期待するコメントがあった。
第二報告・ペラージョ・プリエト・ミゲル・アンヘル氏(京都大学大学院)の「江戸時代の加賀藩における食環境の広がり―舟木伝内の『料理無言抄』を例にして」は、加賀藩料理人が著した食材百科事典をもとに、人間と自然の関係における食を通じた地域特性を報告した。フロアからは、食文化は、時間・場所により変容する動態的なものであるため、研究の射程をどう切り取るかの質問があった。発表者からは出身地であるスペインの食文化の言及もあり、今後の研究の広がりと深化が期待された。
第三報告・榊原真子氏(京都大学大学院)の「首都圏における狩猟採集活動の特質と緑地政策に与える影響」は、都市緑地における狩猟採集活動(Urban Foraging: UF)に注目し、実践者の分類(定着型、ライフスタイル型など)、コミュニティ形成(youtubeなどのバーチャルおよび対面のリアル)、行政との協働可能性(「公共の私物化」を乗り越える)を報告した。フロアからは、都市という公私の区別が明確になる場だからこその特徴や、SNSなどを活用したコミュニティの特徴についての質問があり、農村部での活動との比較や連続性について議論があった。
第四報告・伊藤泰幹氏(北海道大学大学院)の「ヒグマの出没を未然に防ぐ対策はなぜ広まらないのか?―家庭菜園を営む市民のヒグマ出没に関するナラティヴに着目して」は、札幌郊外の家庭菜園耕作者たちがヒグマ対策を行わない要因を分析し、「漠然とした不安」がメディアの影響を受けて形成されつつも、実生活での目撃はほとんどなく、行政や研究者が推奨する対策には当事者意識が薄いことを報告した。フロアとの質疑では、専門家が提示する「正解」と当事者である耕作者にとっての「成解」のズレや融合の可能性が議論された。
筆者の所感としては、堀田氏報告と伊藤氏報告は、それぞれ、公害研究の被害構造論および獣害問題の社会科学的研究の延長にあり、どちらも環境社会学の研究蓄積がさらに進んでいることを感じた。また、ミゲル氏と榊原氏の報告は、自然と人間のかかわりを新しい切り口で分析しており、大学院生による意欲的な試みとして、環境社会学の新しい展開の可能性を感じることができた。
部会C(自由報告)「環境に適応する社会・環境配慮行動」報告
谷川彩月(人間環境大学)
部会C「環境に適応する社会・環境配慮行動」では、対象・方法ともに多様な4件の自由報告が集まった。第1報告の「塩分浸潤に対応する地域社会と生業戦略−ベトナム・メコンデルタの事例」(皆木香渚子)では、ベトナムのKien Giang省An Bien県にある2つの村落におけるフィールド調査から、環境持続性が高いとされる「イネエビローテーションシステム(RSS)」がどのように実践されているのか、またRSSを導入する農家、導入することができなくなった農家にはどのような特徴があるのかが、それらの世帯が耕作する水田の地理的配置や塩分濃度調査の結果とともに詳細に報告された。RSSは循環型の農法のひとつであり、収益性も高いことからRSSの継続を望む農家は多いが、そうした生産者の意向は不可逆的な塩分集積によって阻まれていることなどが明らかにされた。フロアからは、塩分濃度調査やRSSの収益性の詳細を尋ねる質問や、RSSは政策的要請と住民の自主的な適応策のどちらに近い動きなのかを問う質問があった。
第2報告の「環境NPOの収益構造と団体の成長との関連−内閣府・NPO法人実態調査の二次分析から」(藤田研二郎)は、政府統計の二次分析から日本の環境NPOの収益構造を明らかにしようとするものであった。他分野のNPOと比べ、環境NPOは小規模な団体が多く、その多くが助成金を主な財源とする「助成金型」であること、また比較的大規模な団体であっても「助成金型」が一定数を占めており、小規模な団体との資源の競合が起こっているのではないかという考察が述べられた。フロアからは、「団体の規模によって申請する競争的資金の種類が異なり、結果的に棲み分けができているのではないか」という質問や、「サードセクターが多様化している現状において、あえて今回NPO法人に対象を限定した理由は何か」といった質問が挙がった。
第3報告の「環境に配慮した行動の類型化及び影響要因の分析」(陳艶艶)では、オンライン上での全国調査の結果を用いて、環境意識と環境行動が乖離している現状について社会心理学的な枠組みから分析がなされた。分析では、個人レベルの環境配慮行動について「リサイクル」や「節水」、「エコ商品の購入」など合計17項目に対して因子分析が実施されており、4つの因子が抽出されたと報告された。フロアからは、「心理学的なモデリングとしてはどのようなものを想定しているのか」という質問や、「属性などの基礎項目による回答傾向の違いはみられたのか」といった質問が挙がった。
第4報告の「カフェ利用における環境配慮行動に関する分析」(バロリセニア)は、コーヒー業界・カフェでの環境配慮行動に着目し、カフェ利用者を対象としたオンライン調査から、カフェで提供されている5つの環境対策のうち、どんなものが利用者からの認知度や実践状況が高いのかを報告した。分析の結果、認知度は、「紙ストロー」、「フタなし提供」、「マイボトル・タンブラーの持参」、「植物性牛乳」、「サスティナブルコーヒー」の順に高く、また実践状況は、「紙ストロー」、「フタなし提供」、「植物性牛乳」、そして「マイボトル・タンブラーの持参」および「サスティナブルコーヒー」(同比率)の順に高いことがわかった。発表時間の関係で質疑の時間が長く、フロアからは、「利用者の意識と行動以外の要因も関係しているのではないか」という質問や、「どういう環境意識がカフェでの環境行動を促進するという仮説を持っているのか」、また、「環境行動には蓄積性があると思われるか」といった多くの質問が挙がり、活発な議論が展開された。
部会全体を通して、環境配慮行動はいかにして促進されるのかという共通の探究課題がみられ、これは、環境社会学はどのようにして社会変革に関わっていけるのかという根本的な問いに深く関連する課題であるといえるだろう。また、後半2つの報告は社会心理学・環境心理学的な要素も強く、近隣領域との連携あるいは差異化をどのように図っていくのかといった課題も見えてきたように思われた。
大会印象記(富山雄太)
富山雄太(熊本大学大学院)
私は今大会で報告部会、シンポジウム、エクスカーションと全てに参加することができ、大会を通じての感想を書きたいと思います。
自由報告・実践報告部会では主に部会Bを聴講しました。第4報告「ヒグマの出没を未然に防ぐ対策はなぜ広まらないのか? ―家庭菜園を営む市民のヒグマ出没に関するナラティヴに着目して―」(伊藤泰幹氏)では、札幌市郊外地域の家庭菜園耕作者はヒグマの出没をどう捉え、問題に対応しているのかが報告されました。特に電気柵の誤った使い方の語りが興味深かったです。ヒグマの誘引を防止するために果実に柵をしなければならないのに、「漠然とした不安」からか自分たちを守るように家を柵で囲ったという。不安を払拭するためには正しく理解する必要があるが、担い手と期待される住民に、そして漠然とした不安を抱える住民に正しい理解を広めることの難しさを感じました。また時間はかかるが度重なるコミュニケーションで成解を導くという指摘は、市民や行政と環境保全活動を行う私にとっても思い当たることが多く、その重要性を再認識しました。
シンポジウム「環境社会学から問う島嶼の軍事化」、在日米軍基地や基地周辺の暮らしを巡るエクスカーションも非常に興味深く参加させて頂きました。私ごとですが、現在住んでいる家の近くに自衛隊駐屯地や演習場があります。定期的に米軍との共同軍事演習も開催され、自分ごととして問題を捉えて積極的に参加できました。
シンポジウムでは水爆実験に巻き込まれたマーシャル諸島等の歴史が紹介されました。過去を振り返ると当たり前のように太平洋で核実験がされてきました。核実験というと人への被害が注目されますが、核物質による海洋汚染であり環境問題として提起できるという主張は、核実験に対する私の認識を大きく変えるものでした。
普天間基地見学では滑走路のフェンスを隔てて、子供が遊ぶ公園があり、その対比に大きな矛盾と危険性を感じました。そして大きな基地があることで地域が分断されコミュニティ破壊になるという指摘から、公害によってコミュニティが変容する環境問題との類似性を感じ、環境社会学において基地問題を扱う意味も理解できました。
嘉手納基地のゲート近くの砂辺・宮城地区では、その街並みがアメリカ風であることに衝撃を受けました。基地外でリゾート暮らしを満喫したい米軍関係者が移住した結果、地元住民が住み難くなり地区外へ移住するという住民の入れ替わりが起きていました。この地区は伝統芸能が盛んであり、週末になる元の住民らが集まり練習等をしているとのことで、コミュニティの破壊から生じる文化の危機も思い知らされました。
エクスカーションを通じて戦争やアメリカ占領によって強制的に生活を変化させられてしまった沖縄の歴史と、それがずっと継続している事実を目の当たりにしました。そして住民らは何か選択したわけでなく、巻き込まれているだけという現状に強い憤りを感じました。最後にガイドの方が語った、沖縄では散々議論し尽くしたという言葉から、日本全体として基地問題を議論し尽くしたのかと問題意識を抱えたままエクスカーションを終えることになりました。
大会印象記(村松陸雄)
村松陸雄(武蔵野大学)
会員でない、馴染みが全くない学会大会にふらりと参加し、何もなかったように去って行く、ということを、“学会浴”と称して、目下の愉しみにしております。わが国には主要な学術団体だけでも数千を超えて存在すると言われており、同じように“学会”と名乗っていても、専門分野の純度、学際性、発表作法、雰囲気等、千差万別で、多種多様な学会大会の風を全身で浴びることで、大学に所属する研究者として当たり前と思っていたものを疑い、大学人のあり方を再考する好機となります。
私が主宰している研究会(みがく研)の有力メンバーに、環境社会学者を自称する Iさんがいらっしゃるのですが、発する言葉の折々に、物事の本質を鋭く見抜く洞察力、慧眼をお持ちであると感じることがあるのですが、その源泉には、Iさんの学問的ルーツが環境社会学にあるのではと睨んでいます(ちなみに、I さん自身は、最近は本学会活動からとんとご無沙汰とのことで、もしかして幽霊会員?)。そのことを探るべく、機会があれば一度は環境社会学会大会に参加したいと常々思っておりましたが、不思議と奉職先の校務と重複することが数年来続き、今回の沖縄大会で、ようやく初めて参加することが叶ったという次第です。
今回も、他の学会と同様に気楽な感じで参加し、最終日開催のエクスカーションにしれっと潜り込み、立つ鳥跡を濁さず的にすーっと消えるはずが、最終日のエクスカーションの出発地で、期せずして、藤川賢先生から大会参加記の執筆依頼あり。非会員の小生にこのような話が舞い込んでくることは“青天の霹靂”の境地でびっくりしたと同時に、会員と非会員との隔たりのなさに感銘を受けました。学会によっては、非会員参加費を会員の倍以上に設定しているところや、そもそも非会員の大会参加を一切認めていないところもあります。加えて、大会参加費に諭吉(栄一)1 枚が飛ぶようなところも珍しくなく、自腹での参加には躊躇するところでありますが、こちらの参加費は、誰でもセンベロ(1000円)で懐に優しく楽しむことができ、アカデミアに限らず、NPOの方、一般市民等、非会員に幅広く開かれた学会であることの素晴らしさを強く感じました。
自由報告・実践報告に関して、全ての発表を拝聴できなかったですが、私が参加できたセッションは総じて、他学会でありがちな報告者の一方的な発表に終始することなく、話題提供者の発表を端緒とした喧々諤々なディスカッションが巻き起こり、談論風発の現場に立ち会うことができました。さらには、大学院生の発表3件も伺うことができました。学会重鎮の方々を前にすると、往々にして無用に背筋が伸び切った、学位論文の口頭試問的な緊張感あふれる萎縮した発表になりがちですが、いずれの3名も、自由闊達で、若者らしく、常識に囚われない大胆不敵な話題提供でした。大学院進学者数減少等から人文社会科学の危機が叫ばれておりますが、彼/彼女らの珠玉なプレゼンを見て、一筋の希望を見出すことができました。
エクスカーション「沖縄本島中部の軍事基地周辺と地域社会」はすこぶる秀逸でした。丸一日たっぷりと時間をかけて、普天間基地、嘉手納基地の其々周辺をフィールドワークするもので、昼休み休憩も基地内での住民たちの耕作が認められてきた「黙認耕作地」を含めた嘉手納基地を一望でき、平和学習展示室を有する道の駅「かでな」で、バス移動車内でも一秒も無駄にしない(参加者を休ませない)、ツアーガイドの野添侑麻さん(株式会社さびら)による魂のこもったトークレクチャー等、まさに『基地FW三昧』の濃密な一日でした。なお、ツアーの最終訪問先が基地返還後の跡地利用例としての「アメリカンビレッジ」で、当地で買い物等のための自由時間があるものだと勝手に思い込んでおりましたが、実際のツアーでは「アメリカンビレッジ」の入口付近からビレッジ施設を一望するだけだったことも、それはそれで、ちゃらけた買い物タイムが一切ない、硬派(?)な学会主催のエクスカーションに相応しいエピソードとなりました。末筆ながら、エクスカーション企画実施に骨を折っていただきました、熊本博之先生にあらためて感謝申し上げます。
大会印象記(木村元)
木村元(桜美林大学)
印象記を書くのは第57回大会(鞆の浦)の「エクスカーション印象記」以来である。この6年のあいだに職場はシンクタンクから国立大学そして私立大学へと異動したが,社会人博士として社会学を学び始めた頃と変わらず毎回の大会で学びを得ている。
第70回大会(沖縄県立看護大学)に参加した動機は,大会シンポジウム『環境社会学から問う島嶼の軍事化』及びエクスカーション『沖縄本島中部の軍事基地周辺と地域社会』の2つから学ぶことにあった。これまで軍事分野と接点をもってこなかったが,前々職での環境リスク評価・管理の業務経験をもとにPFAS(有機フッ素化合物)に関する研究をおこなうなか,沖縄におけるPFAS環境汚染の背景を知ろうと考えた。第69回大会の部会『公害・環境汚染と市民運動』で報告したように,理論的視点の関係から,研究の重心に置かれているのは軍事施設関連のPFAS環境汚染ではないが,軍事が「社会構造的な“壁”」を構成する要素の1つであるところに接点がある。
大会シンポジウムでは,普天間基地移設問題をめぐる約30年の経緯の詳細を知った。「決定権限なき決定者」という概念を用いた,辺野古住民・名護市民・沖縄県民による抵抗が削がれていった経緯の説明は印象的であった。これはニクラス・ルーマンの用語に基づく概念だが,政府や本土世論が沖縄を決定者として見るにも拘らず,選挙・県民投票などの意思表示が民意として認められるのは政府の意向に沿う場合に限られる事態を指す。「島嶼地域で進展する軍事化」をテーマに掲げた本シンポジウムでは,沖縄に加えマーシャル諸島,フィジー,北マリアナ諸島,グアムの事例について報告された。このような「島嶼」を切り口として問題の普遍性を探る視点の他,1950年前後の核実験を「地球環境問題の先駆け」と位置づける視点なども印象的であった。
エクスカーションでは,(株)さびらによる詳しい説明のもと普天間基地と嘉手納基地の周辺地域の視察がおこなわれた。前日の大会シンポジウムの余韻のなか,軍事基地周辺の地域社会の多様なリアリティを肌で感じる内容であった。多くの学びの一つひとつの紹介は割愛するが,印象的であったのが,かつての激戦地にある嘉数高台公園内の戦争遺跡「トーチカ」での出来事であった。射撃用の小穴を備えた鉄筋コンクリート製のトーチカの出入口は狭いため四つん這いで出入りする必要があるにも拘らず,その中に参加者の多くが代わる代わる入っていったのである。修学旅行の案内もおこなう(株)さびらによると「これほど大勢の大人が入ったことはなかった」とのこと。好奇心旺盛な人々が集う環境社会学会大会にて,今後も学びを得ていきたい。