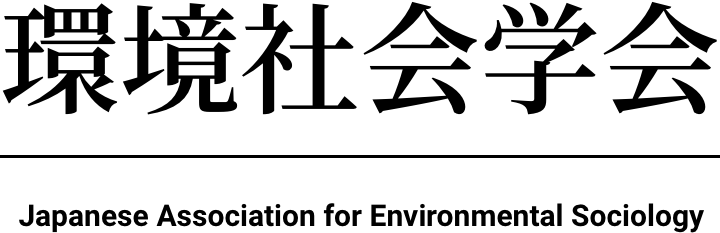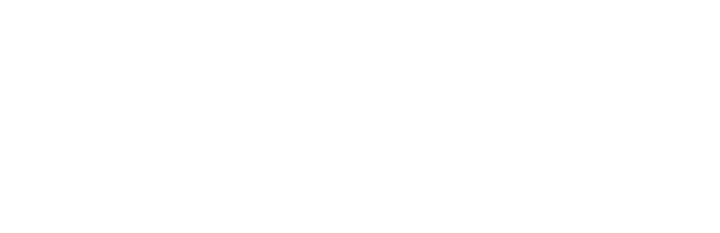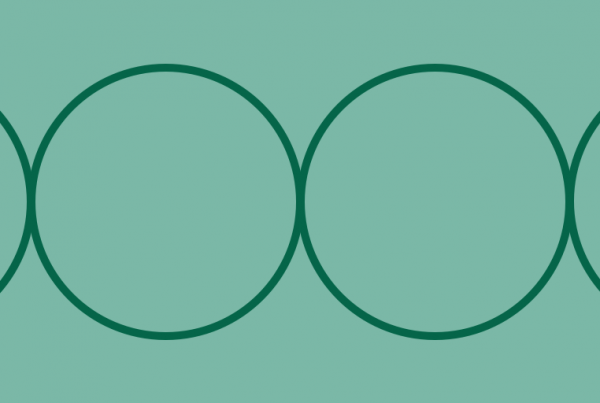環境社会学会は、2025年6月21日~22日に第71回大会を立正大学にて開催しました。大会シンポジウム、震災・原発事故特別委員会企画、部会(自由報告・実践報告)の報告および印象記を掲載します。
大会シンポジウム「環境社会学の課題と展望ー『環境社会学事典』『シリーズ 環境社会学講座』刊行を契機として」に寄せて
関礼子(立教大学)
本シンポジウムの第1部では、2023年に刊行された『環境社会学事典』(環境社会学会編、丸善)について、副編集委員長の浜本篤史氏から編集過程とその狙いについて報告があった。環境社会学の研究を21章構成で網羅的に示し、環境社会学会30年の歩みを収録、地名や英文索引など随所に工夫をこらしたこの事典は、現在の環境社会学の学術としての到達点を示すものである。
本事典で「海外の環境社会学研究」(第10章)などを担当した堀川三郎氏は、日本の環境社会学は「発信」重視の国際化から「対話」重視の国際化へとフェイズを変えつつあることを論じた。また「環境社会学のポジショナリティ」(4章)などを担当した足立重和氏は、社会学としての一分野としての環境社会学というポジショナリティを踏まえつつ、新たな環境社会学の概念・理論の構築を課題に掲げた。
この事典を授業でも活用しているという立石裕二氏は、「『環境』のメインストリーム化と情報化」のなかで、「環境」対策のメインストリーム化は、環境問題の争点を汚染や被害の有無から「指標や数値化された評価の信頼性」=計算結果にシフトさせ、「環境」が企業や国家に影響を与える「権力」になっていると指摘した。
第2部では、2023年から2025年にかけて刊行された『シリーズ 環境社会学講座』(全6巻)をめぐって4つの報告があった。第1巻『なぜ公害は続くのか』に執筆した清水万由子氏は、被害の修復・再生という課題に取り組むうえで、被害者の論理と地域の論理のぶつかり合いがあることを論じ、修復・再生のための「協働」に求められる環境社会学者の実践について課題を提起した。大門信也氏は、ゼミでの実践プロジェクトでテキストを読んだ経験をもとに、「実践へのいざない」が弱くはないか、環境を学ぶニーズに応えられているかを問うた。
山下博美氏は、6巻全巻の各章・各コラムから、それぞれの執筆者の「視点やスキル、態度」を抜き出し、そこから環境社会学の批判性と実践性を論じた。配布レジュメそのものが全6巻のエッセンスを示す貴重なものであった。
椙本歩美氏は、社会の周縁をまなざす環境社会学であるが、その環境社会学のなかで周縁化されているものは何かと問うた。研究者もまたステイクホルダーであり、研究というふるまいが無意識の〈支配―従属〉関係を生み出してはいないかという指摘は、第1部・立石氏による「環境」という権力についての議論とあわせて興味深いものだった。
第3部では、『環境社会学事典』編集委員長の井上真氏と、『シリーズ 環境社会学講座』の最初の5名の編集委員の1人である宮内泰介氏のコメントを皮切りに、フロアーも交えて、活発な議論が交わされた。環境社会学は「知の中心」を目指すだけで良いのか、実践性とは何か、研究者と現場の人の協働とは共に「物語」をつくるということではないか、加害者目線での研究も必要ではないか……。尽きない議論が始まるシンポジウムだった。
震災・原発事故特別委員会企画「災後の『住まう』を考える―津波被災地域の現在から―」報告
髙﨑優子(北海道教育大学)
東日本大震災から15年目を迎える現在、津波被災地域では新たな住まい方が定着したかのように見える。しかしその過程は単純ではなく、復興政策が新たな困難を生む「復興災害」とも呼べる現実が各地で顕在化している。本企画は、宮城県石巻市北上町と同県山元町の事例から、「住まう」ことの模索と制度の作用を検討し、自然災害との向き合い方について議論を深めることを目的として、震災・原発事故特別委員会の企画として開催された。プログラムは以下の通りである。
- 趣旨説明:髙﨑優子
- 第一報告:平川全機(北海道大学)「住宅再建をめぐる制度と選択は何をもたらしたか―宮城県石巻市北上町の14 年―」
- 第二報告:青木聡子(東北大学)「復興構想から外れるという『被災』―宮城県・山元町のコンパクトシティ化と沿岸地域―」
- コメント:菊地直樹(金沢大学)
- ディスカッション
第一報告(平川)では、防災集団移転を軸とした2つの住まいかたが報告された。高台に造成された「にっこり団地」には住宅や公共施設が集約され、結果としてコンパクトシティの一例となった。ここが機能した背景として、メンバーシップや役割が異なる複数組織の連携、ならびに震災前から蓄積された複数集落にまたがる共同経験の存在が、集落の集約化を円滑に進めたことが指摘された。一方で、現地で自宅を再建・修繕した後に災害危険区域に指定された「グレーゾーン」をめぐる困難も明らかにされた。復興スキームから外れたこれらの地域では、インフラ整備や行政サービスの不足など「住まう」困難が集中し、結果として孤立が進行している。北上に住み続ける動機はさまざまだが、復興政策はそれら多様な動機を捨象しつつ、制度に適合しない人びとの「住まう」ことを不可視化し、新たな不平等を生んでいる現実が指摘された。
第二報告(青木)では、復興コンパクトシティを前提とした内陸部の新市街地造成と、沿岸部の災害危険区域指定が、居住継続と生活再建の選択肢を削り取っていく過程が批判的に検討された。沿岸部では、交通・買物・医療など基礎的アクセスの悪化、公共サービスの空白、漁業基盤の断絶が重なり、残された少数の住民にコミュニティ維持の負担が転嫁されている。集会所再建や祭事の復活など、住民による自発的な試みも確認されるが、人口や生活機能の縮減のなか、「住まう」ことの継続には限界も見える。報告では、合理性の名のもとで行われる線引きによって外縁に困難が集中し、「復興構想から外れる被災」が生まれることが明確に批判され、そうした再帰的被災に対するケアの必要性が指摘された。
これら報告を受けたコメント(菊地)では、2024年の能登半島地震の経験を踏まえ、住まいの再建を単なる住宅配置の問題に還元せず、文化や生業を含む生活基盤全体として捉える必要が指摘された。能登における里山・里海の関係や複合的な生業の重要性が示されつつ、状況に応じて一旦撤退し、機を見て再興する選択を開いておく発想にも言及があった。
登壇者によるディスカッションでは、「住まう」ことと合理性をめぐる多層的な議論が交わされた 。能登では里山・里海に支えられた半農半漁的な生業と住まいが密接に結びつく一方、今回の二事例は必ずしも生業密着型ではない。この差異を踏まえると、効率性・経済合理性の扱い方そのものが問われる。住み続ける正当性を生業中心に求めると経済的合理性に絡め取られるおそれもあるため、趣味や土地・環境への愛着といった非経済的根拠も含めて、誰にとっての、どのような合理性かを問い直す必要があることが議論された。また、災後の「住まう」ことをどう支えられるのか、合理性に抗う別の論理をどう紡ぐのかが、今後の課題として浮かび上がった。
続いてフロアからは、人びとの選択肢を狭めていく力学の継続的分析や、現実的選択肢としてのコンパクトシティの多面的評価の必要性が提起された。また、「住まう」ことの意味は豊穣であり、それゆえに法や制度の外での闘いかたを提示するのが環境社会学の役割であるとの指摘があった。
総括として、本企画では、復興政策が構造化する選択肢のなかで、「住まう」ことをめぐる再帰的被災をいかに防ぎうるかが問われることになった。東日本の津波被災地域が示しているのは、災害危険区域指定という制度をつかった合理性の作為的操作である。一方、本企画が射程とする能登半島地震の被災地域では、不作為による合理性の操作がすでに顕在化している。フロアから、「復興とは、ここで死ねるということ」という津波被災地域での印象的な言葉が共有されたように、効率性や合理性といった言葉では捉えきれない「住まうことの尊厳」をどう守るのかが、今後も継続した論点となるだろう。また、継続する事後被災に対して、どのようなケアをすべきかも、実践的な論点である。被災地域は多様であり、その多様さに応じた復興戦略の練り直しが求められる。時間の都合上議論が深められなかったが、報告された2事例のように必ずしも生業と住まうことが密着していない地域において、そこに住み続ける意味や正当性をどう位置づけるのかは、環境社会学の射程を拡張する課題である。求められるのは、再帰的な被災を防ぐための論理を編み直すことである。災害が頻発する社会において、生活の総体を捉える視座を共有し、住まうことの尊厳を守るための議論を継続していきたい。登壇者ならびにフロアの皆さまに感謝する。
自由報告・実践報告 部会A「環境リスクと地域社会」報告
原口弥生(茨城大学)
自由報告4本、実践報告1本という充実した構成であった。“Forever Chemicals”の典型であるPFAS問題という新たなリスク対応から廃棄物行政の実効性に迫る研究、原子力と地域社会をめぐる住民運動、原発事故後の復興プロセス、その陰で進む森林利用という相互に関連するテーマでの部会となり、質疑応答も活発に展開された。
第一報告(中山敬太:自由報告)は、「有機フッ素化合物(PFAS)汚染をめぐるリスクと不確実性の社会構造 ―加害と被害に対する『構造的暴力論』の観点から」であった。PFASの研究開発・製造・消費・廃棄のフローにおいて、環境規制と健康被害との関係はどのように分析されうるか、という視点から報告された。上流部はすでに国の規制対象となっているが、下流部の消費や廃棄段階での環境汚染について国内では暫定基準値のみであり、PFASによる健康被害の因果関係の立証方法なども未確立である。この法の未整備状況は「不確実性」領域と整理され、PFASが幅広い用途で利用され、汚染経路も多様であることを背景に、省庁の縦割り構造や国・自治体の役割等について問題構造が提示された。
第二報告(齊藤由倫:自由報告)の「自治体の普及啓発施策がもつ生活系ごみ削減要因の探索(1)」では、先行研究で費用対効果が示された「廃棄物等減量推進員」と「携帯電話アプリ」の施策について、自治体ごとの導入の契機、行政内部の手続き、推進員と自治体との関係など、共通点と多様な状況が紹介された。このような普及啓発施策は、実施コストが低く立案の自由度が高いことから、自治体の独自性・主体性が発揮される領域である。「廃棄物等減量推進員」の活動は効果が高いと評価されているが、ごみ排出原単位との関連や、自治会・町内会の弱体化による影響があるのか、などについて意見交換された。
第三報告(高野 聡:実践報告)の「核ごみ文献調査を拒否した長崎県対馬市の住民運動に関する研究」では、2023年の文献調査受入れをめぐる地域の住民運動の戦略、住民主体のまちづくりの実践、NUMOの活動の住民の認識など、多様な観点から動向が紹介された。対馬という密な地域の共同性のなかで、地域グループ「核のごみと対馬を考える会」は「分断されたら負け」をモットーに、住民運動により核のごみ受入れにつながる文献調査を拒否しつつも、地域の分断を回避するための配慮にも力をいれた。文献調査の問題点を認識した住民の活動が、次第に住民主体のまちづくりの実践にまで活動が広がっていることが紹介された。
第四報告(小原直将:自由報告)は、「住民参加の伴う原発事故後のまちづくりの議論の課題―『双葉町復興まちづくり 委員会(平成24年度~25年度)』の決定可能性の分析」であった。「人の復興」が掲げられた双葉町では、町民主体の復興に向けて多様な住民参加の機会が創られた。多様な議題設定が可能ではあったが、早期の帰還は困難であるという専門家による放射線リスク認識の提示もあり、実際に町民が決定できた事項は限定的であったことが指摘された。双葉町役場と住民は相互規定的にならざるを得ない状況になりながら、次第に帰還できないことを前提とした役場主導のまちづくりへと展開していったことが示された。事故後のまちづくりという局面において、専門知と生活知の関係性をどうとらえるのか、という点で質疑応答があった。
第五報告(木村憲一郎:自由報告)の、「原発事故から14年を経た福島の森林利用」では、震災前から森林利用が盛んであった福島県における、木材利用、食材利用、空間・土地利用の状況について考察された。14年経過した現在、木材利用では復興需要に支えられ「素材生産量」の好調が続くものの、「山元立木価格」が全国平均より低下したことが紹介された。とくに課題として浮上しているのは、メガソーラーに代表される「林地開発」や里山での「土取り」である。避難指示区域やそれに隣接する地域における空間・土地利用の変化が指摘された。被災地の「復興」が注目されるなかで、その陰で進む周辺の森林利用と景観の変遷は、被災地域の住民と「土地」との関係性の変化を示唆する貴重な報告だった。
自由報告 部会B「食をめぐる制度と言説」報告
福永真弓(東京大学)
昨今、食の研究(Food Studies)はさまざまな専門分野および学融合・領域横断的な研究を含む研究・実践領域として急速に発展している。本部会でなされた発表は、環境社会学がフードシステムのガバナンスや制度設計から、ANT論を応用した生業研究、消費と生産のネクサス形成の研究、サステナビリティが生みだす階層性とアイデンティティ政治など、幅広く多様な分野を論じるプラットフォームとなりうることを示していたように思う。
新井雄喜(松山大学)「水産物認証(ASC)の他地域への波及プロセスと『社会変革』における役割」は、宮城県養殖カキのASC認証の波及過程を事例に、生物多様性保全に資する社会介入点を検討するものだった。質疑では、認証制度の乗り換えによる環境保全効果の低下や負の影響、養殖魚種ごとの環境負荷管理、地域支援型漁業との接続方法、介入パッケージとしての認証制度の評価基準などが議論された。また、カキの低環境負荷や施策の抱き合わせの有効性、地域支援と社会変革の関係整理、流通・小売への働きかけの困難さ、市場メカニズム外の多義的なベネフィットを関係者が得られる仕組みを併用することの必要性などが指摘された。さらに、売上や生産量への影響、消費者訴求よりも企業の調達ポリシーや便益多様化(例:ネイチャーポジティブ)の確保が有効との意見があった。
西城戸誠(早稲田大学)・髙﨑優子(北海道教育大学)・廣本由香(福島大学)「『八丈くさや』の変遷―『におい』と人のかかわりをめぐって」では、ANT論を踏まえたモノ研究を再設計し、人・モノ・意味・制度が織りなすネットワークの変容を描こうとした。加工業者は、においをつくる営みを通じ、社会・市場・地域社会の変化に応じて「くさやらしさ」と「地域らしさ」の相関関係や概念的再編を模索してきたことが示された。質疑では、地域が考えるにおいの真正性の捉え方に関する問いや、嗅覚・においを切り口に文化的差異や集団形成に関する社会的境界を論じる新たな展開への期待が寄せられた。また、ドリアン等、他のにおいを発する食品との比較研究の可能性も指摘された。ANT論におけるエージェンシーの設定についても、文化人類学やSTS論で論じられてきた、エージェンシーのままならなさについての指摘もなされた。
藤原なつみ(九州産業大学)・丸山康司(名古屋大学)「有機農業を支持する消費者の多様性―小規模農園の購入者アンケート調査分析をもとに―」では、小規模有機農園3園の顧客を対象に量的調査を行い、従来想定される健康志向や有機農業・生産方法といった評価軸よりも、農園主への共感や商品の価値といった別の価値観が消費者に重視されていることを明らかにした。質疑では、なぜ3園を対象としたのか、異なる農園との比較の必要性、小規模農園が現代のライフスタイルに適合する可能性、生産者と消費者の新たなアイデンティティ形成の側面などが指摘された。また、認証制度を含む既存の消費者選択の現実を補完的に捉える必要性も述べられた。
紀平真理子(名古屋大学環境学研究科)「奪われた『自然』と選択される『科学』―環境言説の制度化がもたらすオーガニック給食運動をめぐる対抗運動を事例に―」では、環境言説・制度・認識が主流化するなかで、これらに反対する対抗運動に焦点をあて、グリーンのなかに生まれている階層性の所在を明らかにした。階層性や経済的立場の格差を乗り越えるのはアイデンティティの政治だが、乗り越えられない現状を目の前に、個人化されたフレーム同士の競合がおこる。その競合において、「わたしのオーガニック/サステナビリティ」というフレームが生まれ、そのフレームを保持・強化するための科学的言説の動員がなされる。フロアからは、ポスト・トゥルースの時代の環境社会学研究としての展開の可能性や、そのための新たな研究手法が求められることが論じられた。
自由報告・実践報告 部会C「気候変動と応答の多様性」報告
寺林暁良(北星学園大学)
部会C「気候変動と応答の多様性」は、自由報告3本、実践報告2本という構成であった。当部会の司会を担当した立場から5本の報告を振り返りたい。
第1報告は、武蔵野大学の白井信雄氏による自由報告「気候変動への心的飽和を解消する方策──飯田市民アンケート調査の2時点比較をもとに」であった。長野県飯田市の市民を対象に2012年と2023年に実施したアンケート結果を比較したところ、温室効果ガス削減に対する意識の低下がみられたという。その理由として「個人行動への心的飽和」が挙げられたが、フロアからは「心的飽和」という捉え方の妥当性や、心的飽和を乗り越えるための「社会共創の場づくり」の定義や方法などについて質問が出された。これらはアンケートとは別のイベント(ワークショップ)から析出された仮説であり、その検証は今後の課題とのことなので、続報に期待したい。
第2報告は、信州大学大学院の杉本陽太氏による自由報告「太陽光発電事業の社会的受容性──長野県内自治体の応答にみる『推進』と『規制』の複雑性」であった。長野県内の市町村では、太陽光発電設備の設置に対して規制色の強い条例が「ドミノ」のように伝播している一方、コミュニティ主導型の再エネ事業が行われる自治体では、規制強化を避ける傾向があるなど複雑な状況があるという。質疑応答では、日本における「開発前提」の土地利用制度の問題点や自然保護など他の規制制度との関係について意見が出されたが、これらは報告者も今後の課題としており、研究の進展が待たれる。また、社会的受容性の研究としては、条例に対する「住民の視点」がさらに深掘りされることにも期待したい。
第3報告は一橋大学の佐藤圭一氏による自由報告であったが、予定からタイトル及び内容が変更され「エネルギー供給体制と気候変動対策の進展──『社会変動の環境社会学』のためのマクロ・トレンド分析」となった。本報告の目的は、世界主要国のエネルギー供給体制の変化を通じて、マクロ社会変動の理論・手法として「トレンド分析」の有効性を示すことであり、移行パターンが日本などの「再エネ主導脱炭素転換型」とアメリカなどの「脱炭素主導再エネ転換型」の2つに収斂していることが示された。質疑応答では、今回の分析結果とメゾレベル・ミクロレベルの事象とを突き合わせた際の矛盾について議論が交わされた点が興味深かった。日本の環境社会学ではマクロレベルの研究がそれほど多くないが、今後はこうした研究が豊富化し、メゾレベル・ミクロレベルの研究との交流が盛んになることも重要であることを実感させられた。
第4報告は、総合地球環境学研究所/京都府地球温暖化防止活動推進センターの木原浩貴氏による実践報告「京都府亀岡市における学校断熱ワークショップの事例──建築物の脱炭素化を目指す社会運動のひとつとして」であった(川手光春氏・安藤慶彦氏との連名報告)。亀岡市立詳徳中学校では、生徒会が問題を提起し、地元工務店などと連携して教室の断熱を実現したという。本報告は個別事例の実践報告として非常に興味深いものであったが、こうした学校断熱ワークショップの全国的な広がりを「社会運動」として捉えることが可能ではないか、という主張もなされた。社会運動の研究とするならば、こうした取り組みが実現していくプロセスを深掘りすることで、その特徴や展開要因、課題などをより分析的に示せるようにも思われたため、研究の進展を楽しみに待ちたい。
第5報告は、滋賀県立大学の平岡俊一氏による実践報告「地域脱炭素分野における中間支援組織の体制構築の活性化に向けた取り組み──『脱炭素地域づくり推進に向けた中間支援交流フォーラム』の活動報告」であった。報告者は自治体の脱炭素施策を支援する「中間支援組織」の設立を進めるため、2023年から3回の「脱炭素地域づくり推進のための中間支援交流フォーラム」の開催に携わってきたが、行政セクターの実務に繋がらないなど課題も多いという。質疑応答では、2000年代に多数設立した市民活動向けの中間支援組織をどう総括するか、中間支援組織という名称自体にわかりづらさはないか、などのコメントが出た。いずれも実践をさらに前進させるための建設的なコメントであったように思う。
本部会は、個人の心的要因、地域社会での活動、自治体や県の施策、さらには各国のエネルギーシステムと、多様なテーマとスケールの報告が集まった。しかし、それだけに気候変動という大きな課題に対して環境社会学が果たしうる役割の広さを改めて確認する機会にもなり、全体としては統一感のある部会になったように思う。それぞれの報告の後、たいへん活発な質疑応答・意見交換が交わされたことも、その一因だろう。部会を盛り上げてくれた報告者と参加者に改めて謝意を示したい。
自由報告・実践報告 部会D「自然と社会をつなぐ経験と認識」報告
吉村真衣(名古屋大学)
第1報告は、中原淳氏(京都大学農学研究科・自由報告)による「不登校児の母子が農山村の森林に移動する要因 ―岐阜県西濃における不登校児向け『森の居場所』を事例として―」だった。農山村にある「森の居場所」になぜ地方都市・郊外の不登校の母子が通うかについて、とくに移動のプル要因に着目して分析がおこなわれた。プル要因では移動の動機づけとなる要因や再訪・習慣化を促す要因について、母子を取り巻く社会関係や母の社会運動的志向、「森の居場所」での遊び仕事を通した子どもと自然のインタラクションなどについて論じられた。質疑応答では、当事者としての不登校の母子の具体的な状況や論理に分析の射程を広げることの可能性や、遊びを通した子どもと自然との関わりにおける技術のコントロールや、それによって生じる関わりの重層性に注目することの重要性について議論された。
第2報告は、清水拓氏(早稲田大学文学学術院・自由報告)による「『自然相手』の炭鉱労働」だった。産業技術と労働に関する従来の社会科学的研究では機械装置と人間の関係に着目することが多かったのに対し、「自然-装置-人間」の三項関係をとらえることの重要性が示されたうえで、炭鉱において技術者と労働者がいかに自然と対峙してきたかが、機械装置の開発プロセスや、機械装置を労働者が作動させるための技術の多角的な分析を通して論じられた。質疑応答では農林漁業と対比させながら、炭鉱労働における機械化が自然と労働者の関わりにもたらすものは何か、自然条件からくるリスクと技術者の身体との関わりをどうとらえるか等について質疑応答があった。
第3報告は、岩松文代氏(北九州市立大学・実践報告)による「古木の残存から保存への認識の転換と管理方法の模索 ―大学敷地のシンボルツリーをめぐって―」だった。都市環境において植栽された樹木が、当初と異なる価値やリスクをはらむ古木という新たな位置づけになりつつある現在を「古木化社会」ととらえたうえで、大学敷地内のヤマモモが「残存してきた」から「保存する」対象になるのかどうか、「シンボルツリー」となる条件の解明や保存の実践を探る報告だった。職員、教員、学生、樹木医、市民などの関係主体とヤマモモの関係について分析されたうえで、報告者自身の実践も紹介された。質疑応答では樹木を残す是非やその方法について議論があったほか、樹木の保存のありかたとそのための働きかけには多様な可能性があることが指摘され、さらにそこで自然の権利について考慮するかどうかという論点も上がった。
第4報告は、藤井紘司氏(千葉商科大学・自由報告)による「被爆樹木は語ることができるか ―沈黙と分有の記憶論に向けて―」だった。被爆者の高齢化によって記憶の継承が危ぶまれるなか、注目を浴びはじめた被爆樹木を対象に、被爆樹木と人々との絡まりあいを分析しながら、どのような「記憶の場」が創り出されてきたかが報告された。原爆手記やヒアリングから個々の被爆樹木と人との多彩なかかわりが析出され、被爆樹木を単なる「被爆の証人」ではなく暮らしを共にした〈伴侶種〉ととらえる視点が示された。フロアからは、今後の研究過程で被爆樹39本と人々との個別の物語を厚く記述していくことへの提案があり、報告者からは多くの資料が廃棄されてしまっている実態や、長崎では広島ほどの記録が残されていないことが指摘されたうえで、被爆樹1本1本がどうやって生き延びてきた/いくのかについて記録と分析を継続していくという応答がなされた。
本部会を通して、自然と人のかかわりというテーマの射程の広さが改めて示されたように感じる。自然も社会も目まぐるしく変動していくなか、両者のどのような接点をどのように焦点化し、環境社会学として体系的に問題化してゆくか、その新たな展開を期待させる部会となった。
大会印象記(山田龍之介)
山田龍之介(上智大学大学院)
第71回大会は立正大学にて開催され、会場に集う研究者や実践家たちの多様でクリティカルな視点に感銘を受けると共に、議論の中で醸成される学術的対話の意義深さを改めて認識する機会となった。
直近の5月に入会手続きを経た筆者は、本大会への参加が会員として初の学会活動となった。そんな筆者が本稿を執筆するに至った経緯は、3月に実施された本学会主催の修論博論報告会にてコメントを下さった藤川賢先生に御挨拶申し上げた際、本件についてお声掛けを頂いたという次第である。多くの経験豊富な先生・先輩方がいらっしゃる中、僭越ながら新参者の拙い所感を述べさせて頂くことをお許し頂きたい。
さて、学会大会自体ほとんど未経験であった筆者にとって、普段は直接お目にかかることのない先生方が一堂に会し、目の前で彼ら彼女らによる議論が展開されること自体、驚くべき光景であった。議論の詳細に関しては、各部会報告に譲りたいが、大会を通じた印象は2つにまとめられる。
1つには、テーマセッションや自由報告において、忌憚のない議論が学問の蓄積に繋がっている瞬間を間近に感じた点を挙げることができる。プロの学者や実践家にあっても、研究推進主体のみで学問を前進させることは難しい。しかし、議論を通じて個人や少人数では気付かない視点が加えられたり、公聴者の理解や疑問が入ることで論点の再整理や再検討の余地をより明確にすることが可能になる。それぞれの報告を通じては、実社会の構造的問題が丁寧に掘り下げられており、参加者の間で活発な意見が繰り出され、新たな示唆に繋がっていたものと思われる。
また部会によっては、大学院生をはじめ、初めて当学会にて発表の経験を積んだ報告者も見られたが、クリティカルな指摘が飛び交うやり取りにあっても、とりわけ質疑応答が報告者にとってエンカレッジの場になっている点も印象的であった。総会では会員人数の減少が課題とされていながらも、フィールドワークに基づく実証的研究や、理論的深化を目指した若手研究者による報告は、次世代の環境社会学を担う熱意を強く感じるものであり、筆者も背筋が伸びる思いであった。
2点目に、各々が自明としている環境正義について、参加者間で一定の共通理解が形成されており、それが議論の活性化に繋がっているとの印象を受けた。例としては、科学的な専門知の押し付けに見る不正義や、生活知の尊重による他者の合理性理解といった志向が集団の中で醸成され、共通した問題意識が学会そのものを盛り上げているのではないだろうか。特に2日目の自由・実践報告では、筆者は部会Aで拝聴する時間が多かったが、原発や廃棄物処理に係る問題を扱うテーマは、これらの問題意識に基づく象徴的な研究であると位置づけられる。
他にも、震災・原発事故特別委員会企画「災後の『住まう』を考える—津波被災地域の現在から」では、コンパクトシティ化の批判として、会場からは「住まいの合理性について、行政の意向が貫徹される一方、住民の自由は抑制され意思を曲げられている」との意見が挙がり、筆者を含め、多くの参加者が深く頷かされた。
枚挙に暇がないが、各テーマについては簡単に答えが出ないながらも思考を共有し、益々複雑化する現代社会の中で、誰もが環境社会学者として果たすべき役割を模索し続けていることを実感する貴重な機会を頂いたと思っている。
最後に、こうして記述している拙稿が活字として記録頂けるのは大変有難いことだが、その裏返しとして本稿の稚拙さに対し一抹の不安が残る。しかし、いつしか筆者自身が本稿を読み返す際、羞恥を覚えるならば、それは今現在の筆者からの変化の現れでもあると思う。したがって、その際大いに恥ずかしく思えるほど成長できるよう、今後も先生・先輩方から御教授賜り、精進していきたい。末筆ながら、今回お目にかかれなかった先生方におかれましても、改めてこの場をお借りして一層の御指導御鞭撻をお願いし、略儀ながら新人による御挨拶に変えさせて頂くことで、印象記執筆者としての責を塞ぐこととする。
大会印象記(ジョン・セギョン)
ジョン・セギョン(東京大学大学院)
大会の1日目は、シンポジウム「環境社会学の課題と展望-『環境社会学事典』『シリーズ 環境社会学講座』刊行を契機として-」に参加させていただきました。このシンポジウムでは、環境社会学の学問としての立ち位置、これまでの成果、そして今後の課題について議論が交わされ、「中心」と「周辺」という概念を用いた多様な発表が行われました。
まず、「環境」社会学が社会学の中心に位置づけられるのか、それとも周縁に置かれているのかという問題提起がありました。また、学問的地形が急速に変化するなかで、環境社会学が現状をどのように説明できるのかについての省察的な議論が展開されました。
さらに、ミクロなレベルの分析では、環境社会学の問いが「加害-被害」構造の可視化にとどまらず、知識生産の構造や、「ポストヒューマン」思想において問われる人間と自然、人間同士の関係性にまで拡張されるべきであるという指摘がなされました。
加えて、日本の環境社会学が国際的にどのように位置づけられ、これまでの知的遺産を十分に発信できているのかという観点からの報告もあり、現在日本で環境社会学を研究することの意味、そして今後それが何を意味すべきかを考える契機となりました。
また、環境社会学を研究するだけでなく、教育現場にも携わる先生方のお話も伺うことができました。たとえば、『環境社会学事典』や『シリーズ 環境社会学講座』をゼミで活用した際の学生の反応や、理解を深めるための工夫に関する報告がありました。続いて、環境社会「学」を研究し、環境社会学「者」になるとはどういうことかについて学生にどう伝えるかというテーマに関する発表もありました。
環境社会学が学問としてどのような独自性を持つのか、また、環境社会学者としてどのような知識を蓄積すべきか、さらには研究者としてのやりがいや魅力について、具体的なエピソードを交えて語られる場面も多く、学生として大いに刺激を受け、感謝の気持ちを抱きました。
2日目は、部会B「食をめぐる制度と言説」に参加いたしました。この部会では、水産物認証(ASC)をめぐる生産者の行動様式、「八丈くさや」の製造業の歴史と変遷、有機農業を支持する消費者、そしてオーガニック給食に反対する母親たちの行動に関する、計4件の報告が行われました。
各発表では、「環境制御システム論」や「社会変革モデル」、さらには「ANT(アクター・ネットワーク理論)」といった理論枠組みが用いられ、食を取り巻く消費者・生産者・政策・科学知識がいかに複雑に関係しあっているのかについて学ぶことができました。特に印象深かったのは、気候変動という変数が私たちの日常の食生活に深く浸透していること、そして食の配送システムという技術の進展が私たちの生活に密接に関わっており、社会学的探究の重要な対象になっているという点でした。
このように、今回の大会では先端的な研究報告を拝聴する貴重な機会を得られただけでなく、環境社会学という学問の現在と未来、そして環境社会学者としての在り方について深く考えることができました。環境社会学を専門とする者、また学ぶ立場にある者として、自らの役割や今後の学びの方向性を改めて問い直す有意義な機会となりました。
大会印象記(北原壮恭)
北原壮恭(京都大学大学院)
大学院生である私にとって,今大会の参加は昨年6月の第69回大会に続く二度目の参加であった。
初日のシンポジウム「環境社会学の課題と展望-『環境社会学事典』『シリーズ 環境社会学講座』刊行を契機として」は,その題に冠する通り,環境社会学そのものへの問いかけがなされるものであった。
事典と講座本を切り口として環境社会学の現状を考察するにあたって,環境社会学とは何であるかの言及を試みたもの,定義を保留した上で国際性という点に焦点を絞って議論したもの,学生への指導の現場における困難を挙げたもの,環境社会学に関する議論の膠着性を指摘したものなど,さまざまな段階,次元での問題提起と議論が行われた。
シンポジウムの印象記ということで,特に印象に残った二つの点を挙げる。一つは,何が環境社会学であるのかということは不明瞭であるということである。個人的な経験に引きつけて考えてみても,環境社会学を学んでいるつもりではあるものの,読む書籍や論文は幅が広く,一体何をもって「環境社会学を学んだ」といえるのか疑問・不安に思うことも多い。しかし,今回のシンポジウムでは「環境社会学とは何か」という議論が不毛であるとするものや,事典や講座本の位置付けを語る中で一つのあり方を示すもの,中心と周縁という視座で語るものなどがあった。このようにして多様に語られることで,環境社会学の曖昧さは疑問・不安ではなく,学問としての懐の広さとして感じられるようになった。もう一つの印象に残ったことは,環境社会学はまだまだ深化の余地があるということである。環境のあり方が変化しているという外的な要素と,再起的に問い直す社会学の一性質という内的な要素によって,環境社会学は対象を拡大するとともに自身の議論を検証していくのだということを感じた。
議論の展開は広範になされた一方で,それらの議論の多くが解決されることなくシンポジウムは幕を閉じた。しかし,このことは議論の不消化というよりは,我々への宿題として投げかけられたように感じた。一学生としては,その宿題に何らかの答えを導ける日がいつ訪れるのか(あるいは本当に訪れるのか)検討もつかないが,環境社会学の周縁に身を置くものとして常に心に留めておかねばと,気の引き締まる思いがした。
シンポジウム開始前に大会印象記を依頼された当初,私は自身の専門が環境社会学であると自信をもっていうことができないという不安から,一度断ろうとした。しかし,その直後のシンポジウムの内容がまさにそうした不安を和らげ勇気づけるものであった。そして私は卑屈になることはかえって誠実さを欠いたことであると襟を正し,大会印象記を書かせていただいた。翌日の自由・実践報告については紙面の都合上割愛するが,今大会の講演はその発表内容が学びになっただけでなく,自身がこれからも環境社会学に関わっていくための勇気と情熱を与えてくれるものであった。