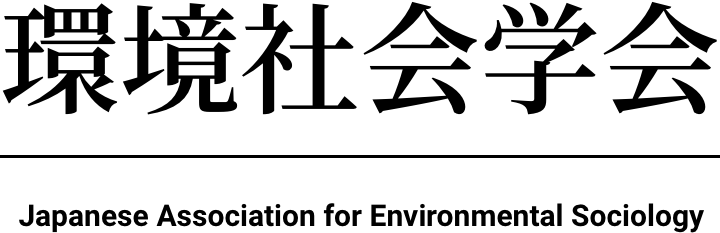環境社会学会理事会は、福島第一原子力発電所事故発生から10年の経過をふまえた被害者救済のあり方について、下記の通り、声明を発出いたしました。
福島第一原子力発電所事故からあと数か月で10年に届こうとするなか、事故の被害者による集団訴訟が全国各地の地裁・高裁、また最高裁で進んでいる。本声明は、国の原子力損害賠償紛争審査会の指針(以下、原賠審指針)が、原発事故による被害者の将来にわたる救済をはばむ障壁となることのないよう、当事者である原因企業、行政、そして司法に対して認識を促すものである。
原賠審指針は、可能な限り早期の被害者救済に寄与すべく策定されたが、損害の全てを網羅したものではなく、状況の変化に応じた見直しがありうること、原因企業の柔軟な対応が求められることをも示している。
にもかかわらず、被害の実態を狭くとらえ、その広がりや多様性・多面性を十分にふまえないままに「解決した」「終結した」とすることは、将来的には問題をより複雑化させ、その解決を遠ざける危険性がある。その危険性を回避するためには、とくに、(1)被害の過小評価、(2)被害の潜在化とその放置、(3)「被害にもとづく賠償」から「賠償総額にもとづく抑制された被害認定」への逆転、の3点に留意すべきである。
(1)被害の過小評価
原賠審指針は、最低限賠償されるべき損害を示すガイドラインであり、被害の総体をカバーするものではない。にもかかわらず、原因企業は、ADRや裁判において、十分な賠償を定めた基準であるかのように援用し、被害を過小評価している。
環境社会学の被害研究の教えるところでは、環境汚染にもとづく被害は、家族生活や地域生活といった社会的な関係性において増幅し、それらが個人の生活に多様な形でふりかかってくる。またこうした社会的増幅は、汚染物質に曝露されていない周辺の人々を巻き込み、二次的な被害をもたらす。
福島第一原子力発電所事故(福島原発事故)被害者による集団訴訟において提起されている「ふるさと喪失(ふるさと剥奪)」という社会関係の次元を視野に入れた損害の指摘は、まさに環境社会学が捉えてきた被害の社会的増幅を司法の場で可視化するものである。問題は、こうした被害の総体を到底カバーしているとはいえない原賠審指針を、原因企業がADRや裁判において十分な賠償を定めた基準であるかのように主張している点である。このような損害賠償の判断は、社会関係のなかで増幅され個々人の生活の様々な局面に入り込む被害の実態を過小評価することにもなりかねない。
被害は、公害問題における婚姻差別が典型であるように、福島原発事故によって設計を変更せざるを得なかった人生の歩みのなかで折々に現れ、時間的に長期にわたって様々な形で社会的に増幅されうる。現時点で顕著に現れている被害だけでなく、将来的な被害も視野に入れた救済策が講じられるべきである。
(2)被害の潜在化とその放置
原賠審指針は、生活全般にわたる被害を不可視化するだけでなく、被害を訴える行為を自己抑制させ、これにより被害の潜在化と被害放置を将来的にも拡大させていく懸念がある。
環境社会学における公害研究は、これまでに理不尽な差別や攻撃など、被害を訴えることにともなう様々な二次的被害を避けるために、「被害者が被害を隠す」ことによる被害の潜在化という問題を明らかにしてきた。またそうした事態は、水俣病認定制度の例に示されるように、救済のための制度によってむしろ促進されてしまうことも明らかにされてきた。被害の潜在化や被害放置は、結果的に問題の長期化につながっており、被害者のみならず原因企業や行政、そして地域社会にとって長期間にわたり大きな負担となっている。
福島原発事故においても、この被害の潜在化および被害放置が生じていることが懸念される。第一に、原賠審指針にもとづく被害の過小評価は、必然的に被害の潜在化を引き起こすことになる。第二に、原因企業の和解案拒否によってADRの打ち切りが相次ぎ、被害者が改めて裁判に訴えざるをえない状況も、被害の潜在化と放置を促進させている。第三に、裁判などでしばしば主張される、原告側の訴えを「一部のものに過ぎない」とする加害者側の言い分は、被害の潜在化の問題を看過し、被害放置を拡大させる契機をつくりだしている。
(3)「被害にもとづく賠償」から「賠償総額にもとづく抑制された被害認定」への逆転
原発事故による被害の賠償は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法にもとづいて、国が同機構を通じて原因企業に賠償原資を資金交付する仕組みになっている。そのため、本来の「被害の考量にもとづく賠償の決定」という過程から逸脱し、「賠償の総額への配慮にもとづいて被害の考量の制限が加えられる」という逆転現象が生じ、被害の過小評価や被害の潜在化・放置が進行しているのではないかと懸念される。
被害者の救済は、本来であれば、まず被害の大きさが考量され、それにもとづいて加害者による賠償の大きさが決められる形で行われるべきである。しかし、水俣病事件にみられるように、これまでの公害事件においては、逆に、賠償の総額(の抑制)が個々の補償を判断する前提となり、認定される被害の大きさを左右するという現象が生じてきた。そして、このため問題の解決が先送りされるという状況が生じた。
原発事故の被害者救済についても、賠償の早期打ち切りが進められ、賠償総額の抑制が図られているのではないかと懸念される。このような対応が続けば、被害放置状況が今後長期にわたり生じることになる。このような事態を回避するためには、現行の原賠審指針の中身と運用を抜本的に見直し、「被害にもとづく賠償」を適切に行うべきである。
政府が東日本大震災の「復興期間」とする10年が経過しようとしている。しかし原発事故により生じた被害の救済は不十分であり、むしろ長期にわたる被害放置を生み出すことが懸念される。現時点において明らかになっていない多様な被害が潜在化している可能性を常に念頭においておかなければ、これから先、20年後、50年後も、原因企業や政府は、被害の顕在化のたびに対応を迫られることになろう。そのような愚を回避すべく、また結果として早期的な問題解決へと至るよう、原因企業、行政、および司法は、現行の原賠審指針に固執せず、被害に真摯に向き合い、公正な判断を下すことを期待する。また、被害実態に即した原賠審指針の中身と運用の抜本的な見直しに、早々に着手すべきである。