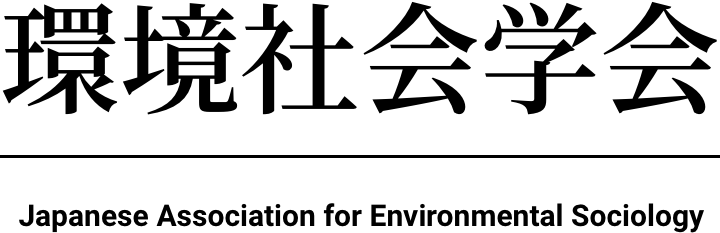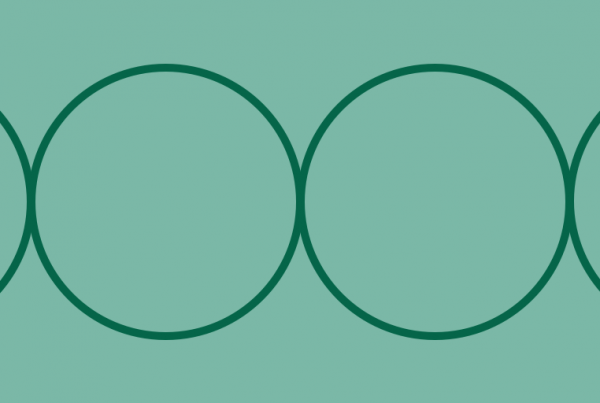環境社会学会は、2021年12月4日に第64回大会をオンラインにて開催しました。シンポジウムと各部会の報告を掲載します。
シンポジウム
グリーン化する社会の環境社会学
― グリーンインフラとどう向き合うか?
菊地直樹(金沢大学)
今回のシンポジウムは「グリーン化する社会の環境社会学 ― グリーンインフラとどう向き合うか?」をテーマとして、以下の登壇者で実施した。
報告者
- 主旨説明 菊地 直樹(金沢大学)
- 報告者1 一ノ瀬 友博(慶應義塾大学)
- 報告者2 鎌田 磨人(徳島大学)
- 報告者3 高崎 優子(北海道教育大学)
- 報告者4 茅野 恒秀(信州大学)
コメンテーター
- 和田 紘希(国土交通省)
- 岡野 隆宏(環境省)
- 田代優 秋(丹波篠山市役所/和歌山大学)
- 丸山 康司(名古屋大学)
コーディネーター
- 菊地 直樹
近年、環境保全や環境への配慮を社会経済活動に組み込む政策や活動が進められている。こうした社会のグリーン化への一つのアプローチとして「グリーンインフラ」がある。グリーンインフラとは自然の多機能性の活用を通して、持続可能な社会と経済の発展に寄与するインフラや土地利用計画である。日本では東日本大震災以降、環境や土木、建築、経済などの様々な分野で注目が集まり、国土交通省や環境省、地方自治体などの計画に反映されている。グリーンインフラの展開において、工学者や生態学者などが提案する「技術的解決策」だけでなく、研究者、行政、企業、銀行、NPO、地域住民の協働と合意形成という「社会的解決策」もまた必要とされている。技術的解決策と社会的解決策の融合という点から、グリーンインフラは地域住民が使える技術を用いて地域のインフラを自治管理するという「インフラの(再)コモンズ化」という側面も有している。環境問題の解決を志向してきた環境社会学は、グリーンインフラとどう向き合えばいいのだろうか。本シンポジウムは、以上の問題関心に基づき企画したものである。
一ノ瀬報告「人口減少時代の生態系減災と地域循環共生圏」では、生態系機能を活かして人々や財産の災害リスクを軽減する生態系減災の視点から、三陸海岸の土地利用の変遷を読み解き、曝露を回避する土地利用の重要性が示された。地域循環共生圏に向けた取り組みが進む阿蘇の事例では、空間的スケールと社会的ネットワークの重層性の中でのローカルガバナンスの向上が重要であると指摘した。
鎌田報告「グリーンインフラとしての海岸マツ林とその自治管理」では、防災インフラとしての海岸マツ林が、放置に伴う遷移や松枯れ病、管理の担い手不足といった課題を抱えるなか、「誰が」「どうやって」「どのような仕組み」で継承できるかという問題が取り上げられた。大里松原(徳島県海陽町)の部落による自治管理と福間海岸マツ林(福岡県福津市)の地域協議会による管理の事例から、地域住民と行政と地域外関係者の関係性によるマツ林の価値創出プロセスの分析から、グリーンインフラの維持・創成には地域自治の強化を可能とするガバナンス型の問題解決が必要であると指摘した。
高崎報告「創造的復興とグリーンインフラ」では、宮城県石巻市の復興プロセスが取り上げられた。現場で進められている住民による集落の跡地再生は、場所にかかわりたい人びとを受け入れるポリフォニー的なインフラ整備であり、グリーンインフラを用いた住民による創造的復興ではないだろうか。暮らす人びとの視点から「よりよい復興」の形成条件をさぐることが、環境社会学者の役割であるとした。
茅野報告「グリーンインフラの環境社会学的分析視角−環境制御システム論の視点から」では、グリーンインフラの展開は環境制御システムの深化として基本的には歓迎されるべきであると指摘した。環境社会学が設計科学を標榜するなら、より計画やプロジェクトにかかわり、自然の多機能性を活用しうる社会的技術を培っていく必要がある。環境社会学の独自性は、自然の多機能性の活用という複雑な問題に対して、複雑さを前提に解こうとするところにあるという。
以上の報告を受け、和田氏からは国土交通省におけるグリーンインフラの取り組みなどが紹介された。岡野氏からは「自然との共生」の達成には、生態系を基盤とした社会・経済への再設計が必要であり、グリーンインフラはその一つのアプローチであるとのコメントがあった。田代氏からはスイッチング・コストの問題があるため、地方自治体においてグリーンインフラの導入が難しいというコメントがあった。丸山氏からはグリーンインフラの社会課題解決策としての特徴として経済・社会・生態系システムが不可分的であるという政策理解、冗長性の担保、多機能化による問題解決の合理性を指摘したうえで、環境社会学が貢献できる点として、ガバナンスに必要な事実や概念の可視化、規範や理念の提示、ガバナンスの仕組み・手法・技法があるとコメントされた。以上のコメントを受け報告者との議論がかわされたが、コーディネーターの力不足により必ずしも議論を深めることができなかった。
本シンポジウムを通して、環境社会学で培われてきた理論と実践知は、自然の多機能性を活用する社会のしくみや政策、制度のデザインについて新たな知見を提供する可能性は示せたと思う。本シンポジウムが、グリーン化する社会における環境社会学の知のあり方を問い直すきっかけになったと期待したい。
部会A. リスク・被害がもたらす影響と対応
廣本由香(福島大学)
部会A「リスク・被害がもたらす影響と対応」では3つの自由報告がおこなわれた。今回の3つの報告に共通していたのは災害(水害、原子力災害、パンデミック)であり、その影響をどのように解釈し、適応するのかということであった。
第1報告は、前田豊氏による「水害リスクの可視化が及ぼす地価への影響について」の共同報告であった。自然災害の発生前に講じる災害対策(災害リスクの可視化)が招くジェントリフィケーションについて、滋賀県流域治水の推進に関する条例の差の差分析(Difference in Differences)から報告された。この分析結果からは水害リスクの可視化が地下の変動を起こし、より浸水リスクが高い地域ほど地価が下落しうる可能性や、ジェントリフィケーションが起こる可能性が示唆されるという結論が示された。報告後にはフロアから、「リスクの偏在性だけでなくて、リスクの偏在の受け手がどのようにかたちで社会的に変動するのか。その分析があれば、ジェントリフィケーションという概念を適応する意味があるのではないか」という質問があがった。
第2報告は、新井雄喜氏による「零細漁民コミュニティにおけるコロナ・パンデミックの影響と適応戦略:タイ・トラン県の事例」の共同報告であった。タイ南西部・トラン県を対象に、新型コロナウイルスのパンデミックが零細漁民に与えた影響と、それへの適応戦略について質的データと量的データの分析から報告された。分析枠組みには、適応サイクルモデルと持続可能な生計枠組みの2つの方法を組み合わせた独自のモデルを提示した。その分析結果では、パンデミックの影響で漁民の漁獲量と収入は減ってしまったが、なかには柔軟な適応戦略を通じて収入を一定程度回復させた漁民もいたことが明らかにされた。フロアからは「生業複合を考えるときに市場経済と生業経済をどう区別しているのか」「零細漁民の適応戦略で、新たな知識等を得ようとした人とそうでない人との違いは何か」という質問があがった。
第3報告は、庄子諒氏による「「被害」の不可視性と笑い:原発事故後の福島におけるユーモアの実践を事例として」の報告であった。福島原発事故後の被災地・福島におけるユーモアの実践に着目し、お笑い芸人の漫才やテレビ番組での被災者による語りの分析がおこなわれた。その結果として、ユーモアの実践が自らがおかれた問題状況に対して笑いを仕掛け、そのリアリティを相対化しようとする試みとして把握できること、そこで生まれる笑いは問題状況を生き抜くレジリエンスを発揮しうることが示された。フロアからは「ユーモアは視点を変えるということであるが、被害を多面的に見ていくうえで笑いがどのように作用するのか」という質問や「笑いが引き起こしてしまう優越性への自覚が重要な分析になるのではないか」というコメントがあった。
第5期震災・原発事故特別委員会では、環境社会学の「応答」をテーマとしているが、いずれの報告にも通底していた災害レジリエンスは「応答」をめぐる議論にもヒントを与えてくれたように思う。
部会B. 現代社会のサステイナビリティ
大門信也(関西大学)
部会Bは「現代社会のサステイナビリティ」と題して、3つの報告が行われた。
第1報告では、「<生産の踏み車>を操るグローバル環境制御システムとしての人類遺産資本の所有権回復モデル――誰も取り残さない環境社会学理論のために」と題して、岡野内正氏が報告した。氏は「生産の踏み車は制御できるか」という問いをもとに、環境制御システム論やエコロジカル近代化論等が前提としている民主主義的資本主義、あるいは国民国家による制御という解決策には限界があると論じる。そのうえで、グローバルな生産の踏み車を回す多国籍企業の過半数株式を、現在のような超富裕層ではなく、人類遺産資本として全人類成員が均分相続し、資源配分に関する意識決定権を全人類に移転することによって、生産の踏み車を市民社会が直接制御するという構想を示した。質疑応答では、人類遺産持株会社のオペレーションの技術的・組織的可能性、課税による(つまり国民国家による)制御可能性との比較、そして手続き的な正当性がはたして確保できるのか等の問題が議論された。
第2報告、陳艶艶氏の「テキストマイニングによる環境意識と行動の斉合性分析」では、2016年に東京都民を対象に行われた質問紙調査(有効標本数519人)のうち、地域環境の保全のために一般市民が取り組むべき課題に関する意見として得られた自由記述を環境意識に関する回答と位置づけ、選択肢項目で得られた環境行動に関する回答との関連性が検討された。結果としてゴミやリサイクルといった日常の具体的な環境問題について言及する回答者は、実際の行動においても同様にゴミやリサイクルなどの個人レベルでの環境行動を行っている傾向がみられ、環境や市民、改革といった抽象的な語を使う回答者は、組織的・集団的な社会レベルでの環境行動を行う傾向がみられるという形で、環境意識と環境行動との関連性が確認された。以上の中心論点のほか、とくに質疑応答では、日本において環境行動を実行する人が若年層よりも高齢層に多いという結果が得られるのに対して、欧米においても、また中国においても若年層のほうが高齢者よりも環境行動を実行する人が多いという結果がえられている点について、議論が交わされた。
第3報告では、天野健作(大和大学)・立花晃(大和大学)が「みどり(Green)」のまちづくりにおける「暮らしやすさ(Suitability)の社会学的研究と指標の開発」を報告した。本報告では、国土交通省による「グリーンインフラ推進戦略」を社会的な要請としたうえで、「暮らしやすさ(Suitability)」をみどりのまちづくりのための鍵概念として、これを計量・比較可能な指標として開発することを目的とした研究プロジェクトの紹介が行われた。研究の中心課題となる暮らしやすさ指標については、「3つのS」(「Suitability(居住適合性)」「Sustainability(持続可能性)」「Studybility(学習可能性)」)と「3つの資本」(文化資本、社会資本、環境資本)をかけあわせた指標化のアイデアが示された。質疑応答では、吹田市との連携による研究推進体制、研究の主軸となる計量的な指標化にあたる妥当性や標準化の問題、また資本概念をめぐる政治的な次元の必要性についての議論が行われた。
「現代社会とサステイナビリティ」という大きな括りのなかで、ヴァラエティに富んだ3報告であったが、総じて環境社会学の中心的議論からはこぼれがちな論点や方法が意欲的に提示された、大変有意義な部会であった。報告者はもちろん、ご議論いただいた参加者のみなさんに感謝申し上げる。
部会C. 地域社会とネットワーク
北島義和(釧路公立大学)
部会Cでは、「地域社会とネットワーク」という表題のもと、3つの報告が行われた。
家高裕史氏による第一報告は、「地域再生産性」を「高校生以下や高齢者を含むあらゆる年代・世代の継続的な居住しやすさ」と定義したうえで、居住の中でもさまざまな機関(学校・職場・商業施設など)へのアクセスという要素に着目し、それに対する鉄道を中心とした公共交通網の寄与を検討する。家高氏は、事例とした福岡県嘉飯山地域の各自治体を、人口変動のデータをもとに「成人時減少後再増加型」、「成人後微減型」、「大学型」、「成人後減少継続型」、「早期減少継続型」に分類し、鉄道至便な自治体では20代後半から30代の人びとの流入があり、地域再生産性が維持されているとした。その後の質疑では、分析手法の妥当性、公共交通網以外の要因の検討の必要性についての指摘がなされた。
朝井志歩氏による第二報告は、鹿児島県の馬毛島における米軍のFCLP(空母艦載機離発着訓練)施設建設計画への地元自治体および住民の対応を検討したうえで、この計画の問題点について考察する。馬毛島は1980年まで住民がいたが、その後は一企業が大部分を所有する無人島となり、2007年にFCLP施設候補地とされ、その後国有化された。地元自治体である西之表市は計画に長く反対してきたが、昨年に市議会で賛成派が多数となった。他方、付近の種子島では住民が賛成派と反対派に分かれ、特に後者は馬毛島との様々な関わりを背景に持ちつつ、騒音の影響、自然環境破壊、基地の町となることへの嫌悪や不安を理由に反対運動を展開してきた。以上を踏まえ朝井氏は、この計画は地元の合意が欠如したまま進められており、地方自治を無化するものであるとした。その後の質疑では、地元概念の精査の必要性、海を通じた島同士の繋がりについての指摘がなされた。
中山敬太氏による第三報告は、地域組織が普段の活動を行っていく中で、地域における平時のリスクコミュニケーションを活性化させる可能性について検討する。事例となる三鷹市では、小学校区単位でその学校に通う児童の父親によって「おやじの会」が結成されており、学校では経験できないことを伝えることを目的に活動を行っている。そして、その活動のひとつである「防災キャンプ」においては、災害時の避難所生活をイメージした体験プログラムが行われており、中山氏はこれを通じて防災ネットワークやリスクコミュニティが形成され、市民や地域全体の防災力の向上につながっているとした。その後の質疑では、判断指標の不明瞭さ、ジェンダー化の問題、コミュニティに入らない人々の存在についての指摘がなされた。
いずれの報告も、調査や分析が現在進行形であり、それゆえの不十分さも感じられたが、従来の環境社会学の枠組みとは異なる研究視点を提供するものであった。このような萌芽的な研究をどのように育てていけるかが、学会としての力量が問われるところだろう。
部会D. 生物と人間社会
Coming soon…