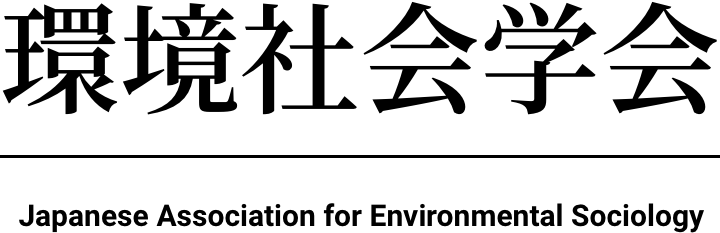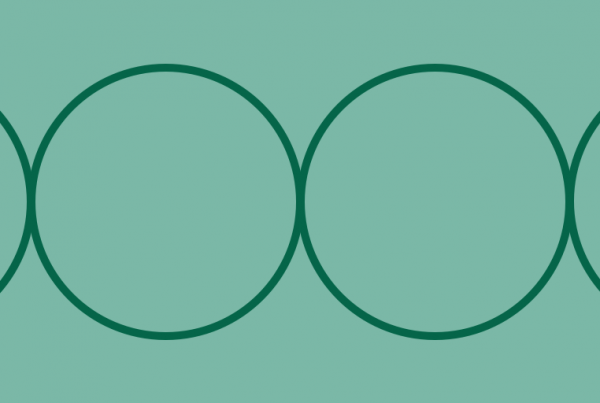環境社会学会は、2022年12月10日~11日に第66回大会を法政大学にて開催しました。シンポジウムと企画セッション、自由報告部会の報告・印象記を掲載します。
シンポジウム「『ソーシャル・イノベーションの時代』の環境社会学―環境問題の創造的解決とは何か?」報告・印象記
藤田 研二郎(農林中金総合研究所)
第66回大会のシンポジウムは、「『ソーシャル・イノベーションの時代』の環境社会学―環境問題の創造的解決とは何か?」というテーマで開催された。本シンポジウムは、2022年7月28日に開催された「B Corp Movementを考える研究例会」から発展したものであり、イノベーションによる社会課題解決に期待が集まるなかで、環境社会学としてそれらをどう捉えるか、主な担い手である企業や経済をどう研究対象とするか、という問題意識から企画されたものである。
まず大倉季久氏(立教大学)から、環境社会学で上記のテーマを扱うことの意義と可能性が説明された。従来社会学では、社会と経済を対抗関係に置き、一定の距離をもって企業を捉えてきたが、とくにパリ協定以降、環境課題解決の担い手として経済や企業への注目が高まっている。本シンポジウムは、経済の内側から企業やそのビジネスを社会過程の一つとして捉え、担い手の葛藤や埋め込まれた関係構造などを検討する試みと位置づけられる。
第一報告では大元鈴子氏(鳥取大学)から、持続可能な水産資源管理を目的とするMSC(海洋管理協議会)認証の歴史が紹介された。1990年代後半、環境NGOが企業と協働する手法としてMSC認証が登場し、2010年前後になると、定着の反面で認証制度の乱立に伴う競争が発生、認証制度自体を審査する機関が設立され、業界内での認証の標準化が進んでいった。とくに小売企業では、認証取得が拡大しており、調達方針への反映や審査の高度化などに展開している。
古屋将太氏(環境エネルギー政策研究所)による第二報告では、イノベーションの主な担い手である企業について、「良い企業」を認証するB Corp Movementが取り上げられた。とくにB Corp企業が自らコミュニティを形成し、ボランティア活動を行ったり、コミュニティ内での取引に発展したり、提言活動を展開したり、といった動きも生まれている。
高橋勅徳氏(東京都立大学)による第三報告では、利潤を求める行為が、どのように社会問題に接続され、ソーシャル・イノベーションに昇華されていくのかが検討された。東京都における林業の6次産業化の事例では、ブランド化戦略として多摩産材に着目した工務店が、当初山主、製材所と利害が食い違っていたものの、とくに助成金への応募や協会の設立を通じて、一企業の戦略にとどまらない「参加者全員の利害」に昇華していった。
第四報告では大門信也氏(関西大学)から、地域自治におけるソーシャル・ファイナンスの可能性が提起された。具体例として東近江三方よし基金は、地域内での資金循環を高めることを目的に、寄付金事業やソーシャル・インパクト・ボンド、地元信金と連携した制度融資、休眠預金活用事業を実施しており、それらを通じて農林水産業や地域の協議会など、社会的事業者への助成を行っている。
従来の環境社会学のなかで、企業や経済の役割を積極的に捉えようという議論は、ほぼなかったと言っていい。一方で、カーボンニュートラルやネイチャーポジティブ、ESG地域金融といったキーワードが経済界でも飛び交い、また社会的企業をはじめ既存の枠組では捉えにくい対象が登場するなかで、本シンポジウムのように企業や経済に改めて着目する試みは、まさに時宜を得たものであろう。筆者自身、環境社会学を一つのバックグラウンドとしつつ、金融機関の末端でビジネスの環境課題解決に関する調査研究に携わっている立場として、非常に興味深く拝聴した。
議論の糸口を探るという本シンポジウムの目的を越えると思うが、以下の点が気になった。認証制度について、比較的順調に普及しているものがある一方で、例えば一部の農産物の認証では、必ずしも有利販売に結びつかず、普及に至っていないものもある。こうした違いは、どのように生じるのだろうか。また、いわば認証ビジネス、コンサルティングが活況を呈する一方で、それに対応できない中小企業が、市場から閉め出されるという事態も起こりうる。こうした事態は、どう捉えたらいいか。さらに企業の取組みについて、優良事例の紹介は多々あるが、それらが置かれている社会・経済的条件は、事例によって異なるはずである。そのなかで何が共通点であり、どのような条件であれば取組みがうまくいくのか。あるいは、うまくいかないとすればなぜか。今後の議論を期待したい。
企画セッション「アフリカ熱帯林の住民参加型マネジメントの模索:実践研究プロジェクトの試みから」報告・印象記
井上 真(早稲田大学)
当学会のメルマガで、この企画セッションについて知った時からいくつかの意味で期待が膨らんだ。まずは、企画セッションのテーマ「アフリカ熱帯林の住民参加型マネジメントの模索:実践研究プロジェクトの試みから」それ自体への興味である。熱帯林/住民参加」/実践研究、という私自身の研究のキーワード的な用語が並んでいたからだ。また、このテーマに相応しい岩井雪乃さん(早稲田大学/「野生生物と社会」学会/環境社会学会研究活動委員)と寺内大左さん(筑波大学/環境社会学会研究活動委員)が企画したセッションである。この二人が企画したのだから面白くならないはずがない。
さらに、話題提供の皆さんがSATREPSの「在来知と生態学的手法の統合による革新的な森林資源マネジメントの共創」プロジェクトのメンバーであった。SATREPSは「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム」の略称で、科学技術振興機構(JST)と国際協力機構(JICA)が共同で実施している途上国との共同プロジェクトである。新たな知見・技術の獲得やイノベーションの創出といった通常の研究を超えて、キャパシティ・ディベロップメントや社会実装を視野に入れているのが特徴である。私自身、かつてSATREPSの審査委員を数年間勤めたことがあり、研究計画策定上の特性や障壁について理解している。そのため、このプロジェクトの皆さんがどんな工夫をしているのか知りたかった。
加えて、「野生生物と社会」学会と環境社会学会は、協定に基づく「連携学会」である。今回のような連携開催は、協定の署名者であった私としてはこの上なく嬉しく、上記の期待を増幅させるに十分であった。
当日の報告内容を余さず整理するのは私の能力を超えてしまうので、一口コメント的に報告しよう。第1報告は、安岡宏和さん(京都大学)による「カメルーンにおけるSATREPSコメカ・プロジェクトの内容と課題」であった。プロジェクトの基盤は「在来知と科学知を統合した持続的野生動物利用モデルの考察」と「ブッシュミートの代替源金収入源となる森林産品生産の確立」という2つの研究である。そして、「地域住民が主体的に参画する森林資源マネジメントの考察」というプロジェクト目標を達成するため、上記の基盤的な研究に基づいて「マネジメントの主体となる住民の育成と実装プロセスの策定」を行う点にSATREPSらしさがあると評価できる。
第2報告は、本郷峻さん(京都大学)による「住民の狩猟活動を基にした野生動物モニタリング:生態学的研究と地域実践との関連付けと実装への見通し」であった。狩猟対象動物の資源量を住民がモニタリングするうえで重要となる「モニタリング指標の開発」と、今後のモニタリングと野生動物マネジメントの実装における課題について述べていた。モニタリングは野生動物マネジメントの一部であり、モニタリングの結果に基づく狩猟制限の意思決定においても地域住民が主体性を発揮することの重要性と、そのため受容可能で実効性のある制限方法の検討が必要であるとの指摘は説得的である。
第3報告は、戸田美佳子(上智大学)さん、四方篝(京都大学)さん、平井將公(京都大学)さん、Ndo Euniceさん (IRAD Cameroon)による「カメルーンの保全政策におけるNTFPsの利用促進とその制限要因」であった。非木材森林産物(NTFPs)の利用を通して経済開発と保全の両立を目指すうえで、地域社会は生産物の運搬や採集のための長時間労働と経済的負担の大きさといった課題を抱えている。そして、今後のガバナンス課題として、狩猟採集民・農耕民・定住商人という三者が課題を共有し協働することで管理当局との交渉力を高めることの必要性を指摘し、より公正な利益配分の実現へと繋げたい、という道筋は大いに評価したい。
第4報告は、カメルーン滞在中の平井將公さん(京都大学)による「カメルーン東部州における森林資源管理手法の社会実装:ガバナンス再編の契機をもとめて」であった。現状における住民による森林利用には、狩猟、植物資源・NTFPsの採集、漁労、キャンプ、木の伐採(蜂蜜採集、キャンプ時の家屋建設)、焼畑、があるが、ことごとく森林法の規定とは不一致であるという実態から如何にして住民主体の管理手法を見出せばよいのか。様々なステークホルダー間のコンフリクトを乗り越えるため、村での集会、有志の募集、長い議論、問題と取組み内容の明確化、調査、定期市場の開催、ワークショップの開催、という手順を踏んでの取組みの困難さを思うと頭が下がる。
以上の4報告に対して2名からコメントがなされた。まずは、梶光一さん(元東京農工大学/兵庫県森林動物研究センター/「野生生物と社会」学会)による「野生動物管理の観点から」のコメントである。先住民の伝統的生業への認識、罠使用についての地域ルール、実態と法律の乖離、管理・モニタリングの単位、フィードバック管理による「為して学ぶ」ことへの住民からの共感、といった実践的な論点・質問が提示された。次は、笹岡正俊さん(北海道大学/環境社会学会)による「東南アジアの住民による森林資源利用の観点から」のコメントである。SATREPSプロジェクトが陥りやすい「政治的な問題を技術的問題に矮小化する恐れ」という根源的な問いかけ、および、モニタリングと違反者への制裁の実施主体、ブッシュミート生産の多元的価値の検討、学びのプロセスが住民による主体形成に与えた影響、といった実践的な論点・質問が提示された。二人のコメントは入念に準備されており、プロジェクトの今後の展開に有益なものだと思う。時間切れのために十分にコメントに沿った議論がほとんどできなかったのは返す返す残念である。
発表者たちにとってのメリットは、自分たちのプロジェクトを知ってもらうことだけではなく、議論を通してプロジェクトに役立てることであろう。なので、やはり発表時間をもっと気にして欲しかった。環境社会学会では、このテーマに関連した議論が展開されてきた。例えば、コモンズ論のスケールを拡大した「協治」論は、外部者を含む小集団のメンバーシップや合意形成の仕組みについて検討してきた。また「順応的ガバナンス」論は、多中心的なプロセスデザインを駆動するための「仕掛け」を日本国内各地の事例から読み取ってきた。議論の時間があれば、このようなプロジェクトにとって有益と思われる観点からの発言と議論の展開も期待できたのではないだろうか。
最後に、コモンズ論ではオストロムによる「3層のルール」が有名である。第1のConstitutional Ruleは制度設立に関する基底的ルール、第2のCollective Choice Ruleは制度で決定された中期計画的ルール、第3のOperational Ruleは具体的な利用規制のことを指す。発表では、法制度の重層性や重要性にも触れられていたが、村レベルで住民たち自身がつくるOperational Ruleの策定可能性も検討する価値はあると思う。
自由報告部会A「環境社会学の実践と方法」報告・印象記
丸山康司(名古屋大学)
A部会では3件の実践報告と2件の研究報告があった。第一報告は関西学院大学の村松淳氏より「学生主体のエコボランティア活動」について実践報告があった。行政と大学が連携しながら神戸市北区の休耕田の再生を行なうという取り組みの経緯や現状とともに課題が紹介された。経済的インセンティブがほぼ無いにもかかわらず多数の学生(大半が女子)が参加したという実践そのもののインパクトに加え、モチベーション維持の試行錯誤など研究としての可能性も感じさせるものであった。体験学習や調査実習として現実の社会課題に取り組む大学も一定数存在するが、これらの実践例を共有しながら意義や方法を深めることにも価値があると思われる。
第二報告は中ヶ谷戸オフィスの松村正治による「市民向け講座における環境運動のパブリックヒストリー実践」について報告された。市民講座という仕掛けを通じて運動性の弱い環境保全活動について当事者の視点や経験を共有する試みであり、実践そのものも運動性を持つというマニアックな仕掛けを興味深く感じた。当事者と受け手の対話的場を作る試みは興味深く、失敗学的な展開も可能ではないかと感じた。
第三報告は水島地域環境再生財団の林美帆氏と大阪公立大学の除本理史氏による「公害資料館における多視点性と協働」である。分断や対立の原因にもなるという意味で公害の継承は困難な課題であるが、それに対して多視点性という考え方を導入した実践が紹介された。全国各地の取り組みをつなげる公害資料館ネットワークと連動した水島での公害資料館の取り組みを通じて、事実認識や解釈の違いを極力包摂するような取り組みを通じて協働の場そのものを維持する試行錯誤が紹介された。分断や先鋭化という課題を乗り越える実践として注目に値する。
第四報告と第五報告は研究報告で、まず関西学院大学の立石裕二氏より「福島第一原発事故後の研究者からの発信は多様だったか?」と題した報告があった。科研費データベースによる専門家のネットワーク分析とメディアでの発言を関連づけた手堅い分析に基づき、原子力工学コミュニティからの距離に応じて研究者の発言のトーンが変化する傾向は見られなかったということや政策への発言状況についてはある程度「ユニークボイス」が存在していることなどが示された。定量的な手法による言説空間の分析として、着実に進捗しており、原子力以外の課題にも応用可能な手法として確立しつつあるという印象を持った。
法政大学の岡野内正氏からは「宇宙環境社会学の課題と方法」についての報告があった。スペースデブリのようが具体的な廃棄物問題や、全地球測位システムの軍事利用など、実質的に宇宙空間における問題が発生していることを指摘した上で、その解決方法として市民資本主義構想の可能性が示された。司会者の理解力不足により全体最適の暴力性が所有関係によって克服可能かという点に議論が集中してしまったが、今後に期待したい。
今回の報告はいずれも新しい領域や手法に取り組もうとする野心的な試みであった。特に実践報告は実践としても興味深く、また研究として発展させる可能性も見えるものであった。このカテゴリーが設けられてから日が浅いが、文字通りの実践だけではなく自然科学的な現場介入や実験との協働など様々な試行錯誤が報告されることに期待したい。
以上の部会の報告とは無関係であるが、この場を借りて一言申し上げさせていただきたい。今回の学会は新型コロナウィルスの感染拡大が懸念される中で久しぶりの対面開催であった。「新しい日常」における学会開催がどのようなものになるか今後も試行錯誤は続くであろうが、一つの実績となったという意味でも意義深い部会となった。準備をすすめて頂いた開催校並びに研究活動委員会に改めて感謝したい。
自由報告部会B「エネルギー・モノ・生物をめぐる環境社会学」報告・印象記
山下博美(立命館アジア太平洋大学)
本部会は「エネルギー・モノ・生物をめぐる環境社会学」という広い枠で、テーマも多岐に渡っていたが、「政策と地域住民の関係性模索」という点で共通項の多い発表が並んだ。
第1報告では、清水拓さん(早稲田大学)が、釧路に再開拓された炭鉱を事例に、石炭の地産地消の現況と経緯を考察した。明治期から栄えた石炭業を地理的・経済的背景からバックアップできることを「悲願」としてきた市や道の言説や、地元石炭を地元発電所で消費するかたちが紹介されると共に、振動や騒音の課題にも触れられた。国や地球レベルで、急速に脱炭素化政策が進む中、地域がその言説との違いをどう理解しているか、地域の理由付けが変化しているのか、について知りたいという質問が多かった。
第2報告の平春来里さん(名古屋大学)は、山形県における「卒原発」へのエネルギー政策転換推進のために実践されている、庄内地方の風力発電事業について発表された。立地地域が政策のフレーミングのみで変化する難しさや、論争が繰り返されてきた地域において、固定化している主体間の「賛成」「反対」の表象に縛られず新たな問題設定を可能にする必要性など、独自の分析フレームワークを提示されていた。「おまけ」と紹介されていた部分も、将来の発展研究を待ちたい。
第3報告は、高木竜輔さん(尚絅学院大学)による 原発事故被災地における避難指示解除が商工事業者の事業再開に与える影響の調査結果であった。福島県商工会議所と共に収集を行った貴重な質問票データを比較し、2016年から2018年にかけて、避難元で仕事を再開していた事業者の割合が14%上昇してはいるものの、避難元に戻った建設業でさえ将来展望が描けておらず、復興事業による被災地再生への影響が限定的であることを示した。商工会との関係性を保ちながら、今後も興味深い分析を見せて頂きたい。
第4報告の、高橋五月さん(法政大学)は、「不安定性」という言葉をキーワードにして、福島原発事故後の海や漁師の生活の様子を考察された。「マルチスピーシーズ民族誌」をけん引する文化人類学者のアナ・チンを引用しながら議論されたが、フロアからは、英語では特にネガティブな意味合いを持つ「不安定性(precarity)」と、環境社会学でよく用いられる「不確実性(uncertainty)」の違いについてより明確にすべきではとのコメントがあり、これらの点を明確にした議論を次回お聞きできればと思う。
第5報告は、梅川由紀さん(神戸学院大学)による、フリマアプリ利用者からみるモノの所有とごみとしての廃棄についての認識調査であった。大変熱のこもった発表スタイルで、梅川さんの学生達が懸命に聞く姿が想像できた。売る人が使ったものが、「モノであり続けていること」を強く望むこと、所有者の使用した痕跡を強く意識すること、家の中で目にみえない「マージナルな」対象を「見える化」していく過程であること、に焦点を当てた点が興味深かった。今回はそれらがフリマアプリ独自の特徴として議論されたが、アナログ時代にもあったバザーや廃品回収との違いを明確にできれば、より深い議論ができそうに思う。
第6報告は、澤井啓さん(北海道大学)が、インドネシア北カリマンタン州にある村の事例を通して、希少種センザンコウ猟の社会的受容性の高い保全策は何か、を考察した。現地での参与観察やインタビュー、狩猟世帯の生計や意識調査など丁寧な研究を行い、現在、センザンコウの個体数や狩猟者が減ってきていることや、保全に対して狩猟者からも積極的な意見が見られたことを紹介した。今なら、地域社会的受容性の高い保全策を提案するよいタイミングであり、慣習法に働きかけていくことが効果的とされた。実際に保全のチャンスに差しかかっていることから、研究者としての実践への関わり方に議論が発展し、フロアからも様々な提案がなされた。
以上6報告が、数年ぶりに対面で行われ、発表時間前後の顔合わせを感慨深く体験することができた。発表者全員が会場参加で、名刺交換をしたり、司会者に挨拶に来て下さったり、あの慌ただしい空気が心地よかった。環境社会学会では、始めて発表させて頂く、という方がほとんどで、新しい研究をお披露目する挑戦の場となっていることがうれしく思った。質疑応答の時間をそれぞれあと5分延ばすことができれば、より深い議論ができたと思われる。今後の皆さんのご活躍と2度目の発表を心待ちにしたい。